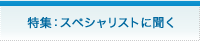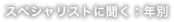国立感染症研究所 ウイルス第三部 部長 田代眞人氏
SARSや鳥インフルエンザなど新しい感染症が次々と出現する一方で、最近は風疹や大人の麻疹(はしか)も増えている。
今回のスペシャリストは国立感染症研究所ウイルス第三部部長の田代眞人氏。私たちはさまざまな感染症とどのように向きあっていくべきか。新しい感染症、情報、教育、ワクチンの観点からお聞きした。(取材日:2004年4月15日)

I.新しい感染症
(鳥インフルエンザ)
-まず、鳥インフルエンザについてはどう向き合えばよいでしょうか。
鳥インフルエンザについては、まだ感染源がわかっていません。今後も繰り返されるかもしれないというリスクもあります。世界各地でこれほど感染が広がったのも、日本で起きたのも、今回が初めてでしたから、当初現場は混乱しました。しかし、日本は技術的にも経済的にも対応が可能です。浅田農産のようなことが起こらなければ、国内で発生する個々のケースについては封じ込めがうまくいくと思います。
今、一番心配しているのは他の国のことです。アジアの途上国では、ほとんどの人々が、鳥インフルエンザの大変さを認識していません。人の健康にとってどれだけの脅威なのか、今何をしなければいけないのか、それがどういう意味を持つのか、そういう知識がないのです。彼らは、いろいろなことを隠しているなどと言われていますが、おそらく悪気はないのだと思います。先進国が「鳥を全部殺せば大丈夫だから、殺しなさい」と言うのは簡単です。しかし国によっては、鳥は大きな収入源ですし、また重要なたんぱく源であり、なくなってしまったら次の日から何を食べていいかわからない、という食糧問題にもつながるのです。宗教的な問題もあります。生きている鳥を目的もなく殺してはいけない、という精神面での抵抗感もあります。感染症のグローバル化に備え、他国の状況を知っておく必要があります。
(SARS)
-田代先生は、昨年SARSの発生後、北京を訪問されています。実際に、現地をご覧になっての感想などをお聞かせ下さい。
SARSの場合、当初、1人の患者が見つかった時に、その人と接触した可能性がある人は全て感染の危険があると考えられていました。そこで、潜伏期を含めて発症後5日目までの患者は感染を広げる心配がないとか、咳が出始めてからが人に広げやすいとか、そういうことがわかってくるまでは、患者の足取りを全部リストアップし、接触した可能性がある人全ての行動を自粛させる、という対応がとられました。しかし、対応が遅れて感染者の数が増えてしまうと、接触者を全て探し出すのは不可能となってしまいます。
そのため、北京では広い地域を封鎖して、そこに居住する3万人を対象とした大規模な隔離・検疫対策をとりました。また北京の病院では医療従事者が2交替制で診療に当たり、1~2週間は自宅に帰らず院内で寝泊りするということも行われました。医療従事者も封鎖区域内の人と同じような生活を強いられたのです。理屈から考えると、そうすれば感染・発症者をその範囲内にとどめることが可能となって効果があるわけですが、実際に行うのは大変なことです。これはおそらく、中国というある意味で特別な国だからこそ、上からの命令で実行できたのだと思われます。
香港では、一人ずつに携帯電話を持たせて自宅待機させ、熱を測ってもらい、警察が毎日、警察電話を使ってやりとりをしました。これも香港という比較的小さい区域だったからこそ、可能だった対策だと思われます。
-1年前のSARSを振り返って思うこと、わかってきたことなどを教えて下さい。
後知恵でしかないのですが、今から考えると、こんなことまでしなくてもよかったのではということがいくつかあります。自宅待機、行動制限、広域封鎖など個人の自由をも奪うことになった対策が、果たして本当に効果があったのか。1年たって、その評価が少しずつ進んでいます。ちょっとやりすぎだったのではないかという評価もあります。
しかし、当時はどこまで手を抜いても大丈夫なのかわかりませんから、最大限の対応をするしかありませんでした。
SARSを教訓に、患者と接する時は常にマスクをする、手袋をする、そういうことを日頃から心がけておけばSARSのような感染症のほとんどは防げるとして、実際に実行している医療機関も結構あります。ただ、一般の日常の診療や介護の場で、スタッフが全員マスクや手袋をしていたら、現時点ではケアを受ける側はかなり抵抗感があるのではないでしょうか。非常に危ないものとして扱われているような不安感を持つでしょう。そのギャップを埋める必要があると思います。
結局、制圧につながったのは、病院の建物や医療行為のすべてを、完全に他の患者から別にした専門病院の設置でした。通常の病院の構造では、レントゲンのポータブル装置や、給食、検査結果などの持ち運びなどの際に、どうしても人の動線が交差します。大病院の一部をSARS専用病棟としても、人の動きを完全に遮断するのは不可能に近いことです。
しかし、SARSに何が効果的だったのか本当のところはまだわかっていないのです。
教訓として得られたのは、そういう事態に至る前に、早く見つけ出し、情報を早く公開し、共有し、対処することの大切さでした。
II.情報
(発信側の心得)
-情報といえば、国立感染症研究所には「感染症情報センター」があります。ここでの情報の収集・発信の際には、どのようなことに注意しているのでしょうか。
感染症の危機管理に情報は非常に大事です。情報には噂や、言葉は適当ではないかもしれませんが、ガセネタ的なものなどいろいろあります。その中から、優先順位が高いことは何か、有効な情報はどれかを、見極めなければいけません。「感染症情報センター」では、どんな些細な情報にも大事なことが含まれているかもしれないから、見逃さないように網を大きく張っています。その中から本当に大事なものを選び出して、必要な情報を適切に伝えるということをやっています。その作業量は大変なものだと聞いています。しかし、その判断を間違えると大変なことになりますから、責任は大きいのです。
情報を出さなければ、風評が一人歩きしますし、疑心暗鬼になります。情報は透明性が大切です。発信側は、常日頃から、世の中から信頼を受けるような情報の提供の仕方を考えておかなければなりません。どういう時に、どの程度危険なのか、きちんと理解してもらえるように努力すべきです。
(受信側の心得)
-情報を受け取る側はどのようなことに注意すればよいでしょうか。
メディアは何事もセンセーショナルに伝える傾向がありますから、それに振り回されないことです。間違った情報が一人歩きしていることもあります。世間はインパクトのある方を注目しますから、声の大きい人の主張ばかり聞こえてきます。
知っている範囲だけですが、SARSにしても、鳥インフルエンザにしても、表に出てこないことがたくさんありました。
情報を受け取る方は、新聞などのタイトルだけでなく中身まで理解しようと意識すべきです。
(情報の一部だけが強調されている例)
例えば、「妊娠中に風疹にかかると大変なことになる」ということは割合知られています。その予防のためにワクチン接種の必要があるというのは大事な情報です。しかし、どういう条件下で、どのくらいの危険でどうなるか、その先が伝わっていません。実際に危険性が高いのは妊娠4~5ヶ月までで、それを過ぎるとほとんど危険はなくなるという情報はあまり知られていません。
たとえ妊娠初期に母体が風疹感染を受けたとしても、そのうち胎児に感染するのは3分の1、先天性風疹児になるのはさらにその3分の1、よって異常を起こす可能性は9分の1です。しかし、風疹にかかった、あるいはかかったと疑われた妊婦が、人工中絶する例が多数あります。これは、情報の一部だけが強調されてかえって悲劇を招いている例です。
(流行情報を把握する)
今、大人の麻疹が少しずつ増えてきています。小児科医が子どもの麻疹を誤診することはめったにないと思いますが、普段麻疹を診ていない内科医は、大人の麻疹を誤診する可能性があります。大人の麻疹は子どもの麻疹と症状が異なります。薬による発疹だと思い、ステロイドを出してしまう医師もいます。しかし、麻疹のような感染症にステロイドは不適切です。
大人の麻疹が増えているという情報が入ってこなければ、あちこちで同じことが繰り返されてしまう可能性があります。
結核も増えてきています。今の流行を念頭において、その可能性を疑ってみなければそれきりです。
医師には、流行を把握し、感染症が変わってきていることを勉強する機会が必要です。
III.教育
(感染症を教育できる専門家が少ない)
-感染症の教育の現状はどうなっているのでしょうか。
職種にもよると思いますが、学校で受ける感染症の教育はあくまでも教科書レベルです。私たちも、エボラ出血熱やペストなど教科書でしか見たことがないものがたくさんあります。何年かに一度しか起こらないような特殊な感染症は、専門家が少数いればいいのかもしれません。専門家以外の人は、自分の手に負えない患者がきたら、どこに紹介すればいいのかがわかっていれば、全ての感染症を詳しく知っている必要はないでしょう。ただ、インフルエンザ、麻疹、風疹、結核、といったポピュラーな感染症への対応を間違えないように、最低限の教育は必要です。
昔の日本では、感染症は大きな問題でしたから、専門家もたくさんいました。特に小児科医はすべてが感染症の専門家と言っていいくらいでした。
しかし、1970年代の後半あたりから、世界中で、感染症の時代は終わったと考えられるようになってきました。日本でも、これからはガンや生活習慣病が中心になる、と言われ、感染症対策が一時弱体化しました。ちょうど今、そのツケがまわってきていて、感染症の専門家が少ないのです。
最近は、感染症全体の重要性が再認識されてきていますが、その受け皿がありません。専門家を育てなければならないのですが、教育できる人が非常に少なくなってしまいました。人を育てるのには時間がかかりますから、中長期的な展望が必要でしょう。
(感染症については専門家以外の発言が多い)
例えば、心臓外科の分野については、専門家以外はあまり発言しないでしょう。しかし、感染症については「インフルエンザと肺炎についてはこうですよ」などと専門家以外でも発言する人がたくさんいます。正しい知識と経験に基づいていれば問題ありませんが、必ずしもそうではありません。誤解を生じる場合もあります。
多くの医師は、ポピュラーな感染症について何回か経験していますから、専門家とまでは標榜しないまでも、自分はそれらの感染症について十分に答えられると思ってしまう人が多いのではないでしょうか。そこは少し意識を変えなければいけないと思います。
IV.ワクチン
(国民の理解)
-厚労省が先ごろ示した、インフルエンザワクチンを優先的に投与するグループの中には医療従事者が含まれていました。これに対するコンセンサスの現状はどうなのでしょうか。
世界的には専門家の間ですでにコンセンサスが得られています。日本では、まだまだ本格的な議論はされていませんが、おそらく反対する人はいないでしょう。医療従事者が現場からいなくなると、医療サービス全体のレベルが下がり、その被害を一番受けるのは国民ですから。ただ、いざワクチンが足りなくなったときに、「医療従事者だけが独占している」などと言われないように、日本でも事前に了承を得ておくべきでしょう。
(医療従事者の心得)
-最後に本ネットワークの会員に向けてメッセージをお願いします。
医療従事者自身の感染を防ぐことは非常に大事なことです。医療従事者は、感染症の患者と濃厚な接触をする機会が非常に多いため、自分自身が感染を受ける可能性が高い。その結果、自分が感染源になる危険がある。医療従事者は大勢の患者を診ますから、かなり多数の人に感染を広げてしまう危険があります。院内感染だけでなく、市中感染の原因にもなります。さらに、医療従事者が病気になると、一般の医療サービスの低下を招いてしまいます。つまり、自分自身を守ること、他の人に広げないこと、この2つの意味で、医療従事者はキーパーソンなのです。
感染対策において、医療従事者は一般の人と大きく違うことを自覚し、積極的にワクチンを接種すべきです。
大切なのは、メディアに振り回されずに日頃からきちんとした感染症の情報を把握すること、そして医療従事者は積極的にワクチンを接種すること。
田代氏も、海外出張の際はワクチンを打っていくそうだ。自ら実践している氏からのメッセージをしっかり受け止めたい。