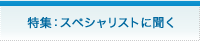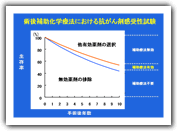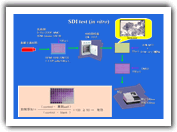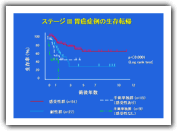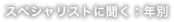近年、がん治療においては抗がん剤の役割が増えつつある。手術、放射線治療、化学(抗がん剤)療法を組み合わせる集学的治療が拡大していること。抗腫瘍効果の高い製品が相次いで発売され、ケースによっては抗がん剤の併用療法だけでなく単独療法としての期待も高いことなどの背景がある。しかし、抗がん剤療法では、効果がなく治療の必要な有害事象(副作用)のみが発生することが少なくない。患者のQOLを著しく損なう場合もある。そんななか「効く」「効かない」を事前にチェックする抗がん剤感受性試験が "高度先進医療" として始まり、一定の成果をあげている。わが国でいち早く取り組んだ慶應義塾大学医学部の久保田哲朗教授にお話しを伺った。
抗がん剤感受性試験とは
がん治療において抗がん剤による治療を行なうのは、2つのケースに大別できる。手術後、局所再発を防ぐための術後補助化学療法として、もうひとつは手術や放射線による局所療法では効果の及ばない進行がん、再発がんに対する治療法としてである。一般に前者は治癒を、後者は延命を治療目的とする。最近では術前化学療法といって、手術の適応に入らない大きさの腫瘍を縮小させ、手術適応にするために用いることもある。
いずれにしろ、抗がん剤療法は施行してみなければ効くかどうかはわからないという一面がある。
「同一の臓器由来で、同一の組織型を有するがんでも、抗がん剤に対する感受性は異なります。つまり胃がんなら胃がんで、病理学的に同じ組織型をしていても、患者さん個々によって同じ抗がん剤を投与しても、効いたり効かなかったりするのです。抗がん剤感受性試験は、この現象を前提として開発されたのです」
久保田教授は抗がん剤感受性試験が誕生した経緯をそう説明しつつ、ひとつのグラフを指し示した。
表1は、術後補助化学療法の有用性を表したものである。手術をして、その後、術後化学療法を行った例で、実際に抗がん剤が効いたケースはどれくらいあるか、グラフ化したものだ。
「それらをよく見て検討すると、手術単独でも治癒した(=補助化学療法不要)例が数多くあります。これらは補助化学療法は必要がなかったといえます。また、補助化学療法が効かなかった人(=捕助療法無効)もかなり多い。この人たちは少なくとも当該の抗がん剤は必要がなかったと言えます。本当に薬が効いたのは、それらを除いた例で、グラフでいえば、ごく狭い範囲(=補助療法有効)に限定されているのです。そういったことを踏まえて、抗がん剤感受性試験は、第一に無効薬剤を排除する、第二に有効な薬剤の選択肢を指し示す目的で行なわれているのです」
現在、よく行なわれている抗がん剤感受性試験の方法は、手術などで摘出したがんの組織を切り取って、in vitro(試験管)でがん細胞を増殖させた上で、いろいろな抗がん剤を投入し、がん細胞の「生き死に」を見るという方法である。がん細胞の増殖法や判定法による違いはあるが、よく行なわれている順にSDI法、CD‐DST法、HDRA法がある。「たとえばSDI法では、がん細胞と各種薬剤をキットの中で48~72時間接触させて、発色によってがん細胞の生き死にがわかるようになっています」(久保田教授)。図1はその工程だ。
対象となるがん種としては、胃がん、大腸がん、食道がん、頭頸部がん、乳がん、肺がん、がん性胸膜・腹膜炎、子宮頸がん・体がん、卵巣がんなどである。
抗がん剤感受性試験の精度については、「第30回制癌剤適応研究会」の全国調査で、臨床効果予測率が示されている。それによると測定・評価可能な病変を有する1101例での正診率は74%であった。正診率とは試験で有効と判定された薬剤が臨床でも有効であった真陽性例と、試験で無効と判定された薬剤が臨床でも無効であった真陰性例を足して、全試験数で割った率だ。久保田教授はこの結果を次のように解説する。
「この調査でわかった特徴的なことは、試験で無効であったが臨床では有効であった偽陰性例が少なく、真陰性率が93%に登っていること。つまり抗がん剤感受性試験で無効と判定された薬剤の9割以上は無効である点です。しかし真陽性率は約46%に止まっています。試験で有効と判定された薬剤が臨床でも有効な率は半分近くある、とも言えるし、逆に半分にも満たない、という見方もできます。従って現状では、抗がん剤感受性試験は、有効な薬剤の選択肢を指し示すというより、効かない薬剤をはねる検査としての有用性が高いといえます」
表2は一例として胃がんの術後補助化学療法における抗がん剤感受性試験の有用性を示したものである。
実施施設は高度先進医療、先進医療として実施
抗がん剤感受性試験は、当初、高度先進医療として医療施設が申請し、厚生労働省の承認を得て行なわれていた。高度先進医療とは、まだ確立はされていないが、有望な治療法・検査法を臨床で提供するため、その先端的な技術部分だけは患者の実費負担で、他の一般診療部分は保険診療で行なうというものである。抗がん剤感受性試験は1990年代半ばよりこのシステムの範疇で行なわれるようになった。「承認のハードルは高く、私どもの施設でも、最初は胃がんにおける試験だけでやっと認可され、大腸がんにおける試験が認められたのはその数年後です。その際、膨大な論文提出が要求されました。それができるのは大学病院など限られた施設といってよかったと思いますが、昨年(2006年)10月に、高度先進医療は先進医療へと衣替えをして、承認のハードルがぐんと低くなり、基準を満たした医療機関であれば実施しやすくなったと言えます」(久保田教授)
表3は高度先進医療として抗がん剤感受性試験を実施していた医療施設の一覧表である。2007年現在では14施設が "先進医療" として承認され、実施している。承認状況については厚生労働省のホームページに掲載されており、閲覧は可能である。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan02.html
ちなみに抗がん剤感受性試験の技術料は、試験法による違いはあるが、およそ3~7万円ほどである。この金額であれば、実費負担であっても、受けたいと希望する患者は多いのではないか。もちろん試験の概略と意義をしっかりと伝え、インフォームドコンセントの手続きを経なければならないのは言うまでもない。
実際の施行例
久保田教授が持つ症例で、抗がん剤感受性試験が効力を発揮したと思われる例を紹介する。
50歳代のJさんは胃がんの手術をして3年後に肝転移が発見された。胃がんの肝転移の予後は大腸がんのそれと比べてかんばしくない。そこでJさんは、胃がんの手術時に採取されていた抗がん剤感受性試験の結果をもとに化学療法を行うことになった。一般には5-FUという抗がん剤を用いることが多いのだが、試験ではその薬剤に対する感受性は低く、シスプラチンという薬剤で陽性と出ていた。ちなみに現在広く用いられているS‐1は承認前であった。この結果を踏まえ、シスプラチンの1週間ごとの肝動注による投与を行ったところ、5週目には肝転移巣がすべて画像上では消失した。結果的に、Jさんは平均的な生存期間を上回り、2年以上存命したのである。
「このケースで、もし標準的な5-FUを投与していたら、がんはほとんど縮小せず、副作用のみが出て、Jさんには無用の苦しみを強いていたかと思います」(久保田教授)
抗がん剤感受性試験を実施していない場合、通常は臨床試験で確認された標準療法、もしくはそれに順ずる療法を全例に対して施行する。当然、効かない例、すなわち治癒や延命という治療目的に寄与しない例が多数出現する。現状の医療技術ではやむを得ないとはいえ、効かない抗がん剤は無駄な副作用を患者に与えるだけである。抗がん剤感受性試験の有効性を示す臨床試験は世界的に見てもまだ充分でなく、したがって確立された手法とはいえないが、無駄な抗がん剤療法による副作用を排除するには、かなり有効な検査法であるのは、これまでの趨勢からしてほぼ間違いないようである。
課題と展望
では抗がん剤感受性試験によって抗がん剤療法のリスク管理は行なえるのであろうか。
「試験によって、効かない抗がん剤を当てることは90%の確率でできるので、無駄な抗がん剤治療による副作用は、結果として回避できます。ところが患者さんは効かない抗がん剤を事前に当ててもちっともありがたくありません。患者さんが欲しいのは自分にとって効く抗がん剤がどれかという情報です。現状の技術では50%弱の確率でしかそれは予見できませんので、まだ効く抗がん剤を調べる検査としては不十分です。効かない抗がん剤を当てるためだけに試験を行なうことはできないので、抗がん剤療法のリスク管理をするには、まだ道半ばの段階です」(久保田教授)
ただイリノテカンや5-FUなど、多くのがん種に対して広範に用いられる抗がん剤に対して、先天的に弱い人たちが存在する。肝の中の分解酵素が少ない、あるいは欠損しているからだ。そういった人たちに、通常の量の抗がん剤を投与すると、重大な有害事象(副作用)が出る確率は高くなる。それを血液などの遺伝子検索により事前に察知して、その抗がん剤の投与を回避する、あるいは用量を少なくするといったようなリスク管理は、実際に行なわれているそうだ。
一定量のがん組織を採取していなければ行なえない、というのも抗がん剤感受性試験の課題だ。
「この試験のことがマスコミで紹介されたりすると、問い合わせが殺到します。その多くは進行・再発がんの患者さんたちですが、すでに手術が終了しており、がん組織が採取できないケースがほとんどで、お役にたてないことが多いのです」と久保田教授は残念そうに言う。
今後は、少量の検体(組織)があれば検査可能な分子生物学的な手法が日進月歩の勢いで発展しているので、内視鏡でごく少量のがん組織を採取する、もしくは血液を採取して、がん細胞の遺伝子や増殖に関わる遺伝子およびたんぱく質とその活性を調べて判定する方法が可能になるであろう。
抗がん剤感受性試験が治癒や延命に寄与するかどうかを検討する臨床試験も、現在行なわれている。試験を行なって抗がん剤を投与する群と試験を行なわないで投与する群との治療成績を比較するのである。そこで抗がん剤感受性試験の有効性が実証されると、これから先、保険適用の途が開けるかもしれない。
<取材を終えて>
抗がん剤療法は、今、入院をせずに外来で行う外来化学療法が急速に広がっている。自宅から通いながら抗がん剤療法を受けるのである。白血病などの一部のがんを除けば、ほとんどの領域のがんで、外来化学療法は可能だという。好むと好まざると、患者が抗がん剤の副作用管理を自己責任にて行なわなければならなくなっているのである。白血球の減少など、いざというときは救急体制を敷いているので、受け入れ可能だとはされているが、現実にはその体制には施設間格差があるのも事実である。抗がん剤感受性試験により、無駄な抗がん剤治療が回避できれば、緊急で医療施設に駆け込む頻度は少なくなるのではないかと思われる。だが久保田教授が指摘したように、効かない抗がん剤を予見するためだけに試験を行なうことはできない。願わくば、効く抗がん剤を予見する確率も90%ほどになり、早く保険適用になればよいのである。そうすれば抗がん剤療法を受ける患者のすべてに抗がん剤感受性試験を実施することができ、結果として大幅に有害事象を回避できるようになるのは間違いないだろう。
取材 黒木要