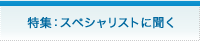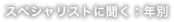東京都立駒込病院 輸血・細胞治療科 比留間潔氏
ウィルスに感染した輸血用血液が検査をすり抜けたというニュースが世間を騒がせてから約1年、厚労省は、血液製剤の遡及調査を8月15日から実施するという通知を出した。また最近、日本輸血学会は自己血輸血の実施率が増加しているという調査結果を発表した。一方で、不適合輸血による医療事故報道も後を絶たない。そこで輸血医療の現状と課題について、東京都立駒込病院、輸血・細胞治療科の比留間潔氏に伺った。(取材日;平成16年8月4日)

輸血医療の現状
(検査の限界)
昨年のすり抜け問題は、輸血によるB型肝炎感染が発端でした。感染した患者さんが2年ほど前に受けていた輸血が原因ではないかということで調査が始まりました。現在は、日赤が世界で初めて導入した核酸増幅検査(NAT)をもってしても、献血者が感染直後でウィルス量が少ないと検出できず、すり抜けをゼロにはできません。しかし、B型肝炎は微量なウィルスでも感染源となる恐れがあります。このため、検査で陽性となった献血者については、献血歴を調べ、陰性だった過去の血液も回収する必要があるとされています。献血者が感染しても検査でウイルスを検出できない期間をウィンドーピリオドといいますが、B型肝炎の場合、44日といわれます。しかし、献血血液を44日間、置いておいてもウィルスが陽性になるわけではありません。ウィルスはあくまでも体内で増えるものです。だからこの献血者が44日後にもう一度検査をしに来なければわからないわけです。
それでは、献血者には必ず頻回来てもらうようにすればよいではないか、と思われるかもしれません。しかし、男性が200mlの全血献血を出来るのは年に6回以内、献血間隔も4週間以上必要です。同量の献血を女性がする場合、年に4回以内となっています。成分献血でも男女ともに最低2週間以上の間隔が必要です。
しかし、血小板製剤の有効期限は3日しかありません。
それから考えると、日赤は極めて安全性を破綻する行為を行なったわけではないのです。ただ、このような献血をした患者がいたら、遡って調査すべきでした。そういう努力をしなかったのは確かに日赤の落ち度です。しかし、これは現在ある輸血のリスクの範囲内のことです。こういうリスクがあることがわかった上で、患者さんから同意書をいただいて輸血をするのが今の基本です。このようなことが、報道によって正確に国民に伝わらず、いたずらに輸血の危険性だけが強調されるとしたら、大きな問題と思います。
(自己血輸血は安全か?)
当院でも自己血輸血を推奨し、実施も増えています。しかし、自己血イコール安全とはなかなか言えません。輸血のリスクを考える場合に一番ピンと来るのが感染の問題でしょう。しかし、実は一番問題なのは血液型の取り違え(不適合輸血)です。これは医療機関がどんなに注意しても一定の確率で起きてしまうという厳然たる事実があります。日本には正確なデータがないのですが、米国には輸血により死亡した場合FDA(米国食品医薬品局)に報告する制度があるため、データがあります。それによると、不適合輸血が発生する確率は約3万分の1、死亡の確率は約60万分の1という数字が出ています。これはB型肝炎やHIVに感染する確率よりも高くなっています。つまり、自己血といえども取り違えられる危険性を含んでいるということです。
患者さんが肝炎ウイルスに感染している場合もあります。本人に返すからいいと思うかもしれませんが、その自己血を取り違えたら大変なことになります。自己血の取り違えは、日赤血の取り違え以上に非常に危険です。
また、日赤血は健康な人から採っていますが、自己血は患者さんから採らなければなりません。患者さんは病気を抱えているので、採血するときの合併症を起こす確率が健康な献血者より高いという問題があります。これに関するデータもあります。(自己血輸血学会のアンケート調査によると、自己血採血時の副反応発生率は1.5%。日赤血献血ドナーの副反応発生率は0.8%。また米国では採血にともなう入院を要するほどの重症症状の発生頻度は、献血では20万回に1回であるのに対し、自己血では1.7万回に1回とされている。(出典:「輸血学-理論と展望」北海道大学図書刊行会)
さらに自己血は細菌汚染が発生しやすいという問題があります。採血の際の消毒をきちんとしないと皮膚の細菌が血中に入ってしまうのです。また、体調が悪いと知らないうちに血中に細菌がいることも、少なくありません。例えば、大腸の病気がある人から採血すると、腸管から血中に侵入した細菌による汚染が発生しやすいと考えられます。実際に、こうした細菌汚染のリスクが、自己血の方が日赤血より高いというデータが報告されています。
また、日赤の場合は献血のプロの看護師が行ないますので、品質の一定した採血が出来ています。しかし医療機関の自己血採血はそうはいきません。輸血部門がない、輸血責任者がいない、そういう中で採血している病院が少なくありません。採血のための消毒法、採血時に副作用が起きた患者への対応法など、輸血の知識を熟知していない人が行なっていることが多いのです。日赤はクオリティの高い管理をしていますが、輸血部門のない医療機関では、採った血液を輸血までどのように保存しているのかも疑問です。
しかし、医療機関は自己血を行ないたがります。何故かというと、1単位(200ml)使った場合に保険請求できる輸血料は、日赤血は450点(1回目)ですが、自己血(液状保存)は950点で、自己血輸血の方が診療報酬が高いという背景があります。また、日赤血は薬価差ゼロで、1単位5~6千円で購入しなければなりませんが、自己血なら支払う必要がありません。そのため輸血管理体制が整っていない医療機関でも自己血輸血を実施したがりますし、行なっているのが現状です。
ただし、自己血には日赤血にない精神的なメリットがあると思います。それは、いわば患者さんがご自身のために献血するという行為ですので、治療に参加する意識が出て、闘病意欲が高まるということです。手術までに貧血を改善するために、少しでも体調を良くしようという気持ちや、医療関係者とのコミュニケーションも深まるということです。
(自己血から無輸血へ)
実は、米国では自己血の意義が薄らいできつつあり、無輸血を推奨する方向に進んでいます。ここ数年間でも、手術でなるべく出血させないような取り組みが進んできています。採血時の貧血や細菌汚染のリスクを考えたら、自己血を採るぐらいの患者にはなるべく無輸血で行い、どうしても必要な場合は献血血液を使うというのが米国のトレンドです。
また、米国は医療費にも敏感です。自己血をたくさん使うと結局トータルの医療費は高くなります。めぐりめぐって国民の負担は大きくなります。医療機関側の立場だけで考えれば自己血の方が儲かりますが、国全体の視点で医療費を見たら、実質、自己血のメリットは少なくなっているというわけです。
課題
(国の主導権が必要)
輸血用血液製剤でよく使われるのは、赤血球、新鮮凍結血漿、血小板の3つです。このうち特に新鮮凍結血漿の使用過剰が問題となっています。新鮮凍結血漿を日本ではフランスの5~6倍、多く見積もると10倍ぐらい使っていると思われます。輸血製剤を安易にたくさん使うことは、知らないうちに献血者に負担をかけることにもなります。
使用過剰を抑えるためには、各医療機関内に輸血の専門部署を設け、適切な輸血療法を常に情報発信し、使用基準が守られているかチェックするようなシステムが必要です。しかし、日本でそれが出来ているところはかなり少ないのです。また、仮に医師が使用基準を知っていても、自分のポリシーと異なる場合、基準を無視して使っているのが現状です。
米国には適正使用基準に加え、適正使用を勧めるためのガイドラインまであります。輸血部門に専門の職員を置いたり輸血療法委員会を作ったりすることで輸血をチェックし、問題が生じたときはすぐに臨床医に伝える、そういうシステムを作るように書かれています。
フランスにはさらに厳しいヘモビジランス(Hemovigilance System;1993年1月4日に制定された、献血から輸血におけるすべての安全性を警戒するシステム)があります。薬害エイズの反省を元に、国の法律で、輸血を行なう医療機関には輸血監視職員を置き、輸血を必ずチェックすることが義務付けられました。監視職員の多くは麻酔科医ですが、血液専門の内科医、薬剤師が担当することもあります。医療機関内で行なわれた輸血を全てチェックし、副作用の有無などを、必ず国に報告しなければなりません。
日本では、厚労省から出されている「輸血療法の実施に関する指針」の中で、輸血療法を行なう医療機関に対して、次の4つの業務体制をとることが推奨されています。(1)輸血療法委員会の設置、(2)責任医師の任命、(3)輸血部門の設置、(4)担当技師の配置。
しかし、この指針そのものが周知されていませんし、守られてもいません。
そのため基本を知らないで輸血を行なっている医療機関が結構あります。例えば交差適合試験は、試験管に受血者の血液を入れて、次に輸血用血液を入れて(もちろんきちんとした濃度に希釈して)、きちんとした回転数で遠心して、凝集の有無を判定するのが正しいやり方です。しかしガラス板の上に血液をたらして、それをぐるっと回しただけで判定している病院があるとの報告を受けています。私たち専門家から見たらとんでもない話で、その程度ではとても正しい判定は出来ません。もちろん医師は悪気があって行なっているわけではないでしょう。輸血に関する新しい情報が入らず、医師の裁量だけで続いているのだと思われます。
日本は先進諸国の中でも輸血をする医療機関が圧倒的に多く、東京都の調査によると都内で輸血を行なっている病院は約600あるそうです。人口比からみてもわが国では他の国より、非常に多くの病院で輸血が行なわれているのが現状です。
日本は平等な医療をめざしていますから、どんな医療機関でも輸血を行なっていいことになっていますが、それを少し変えた方がいいかもしれません。
こうした状況を招いたのは、国が指針を周知徹底させる努力をしてこなかった側面もあるでしょう。例えば、国立病院や日赤病院ではいまだに輸血部門が設置されていない病院が多いのです。また、国立大学病院でも輸血部門の専任教官を廃止するというとんでもない動きが出ています。
フランスでは国の法律にしたから出来たことが多いのです。日本も国が現実性のある強い指導力を発揮しないとできないでしょう。指針に書いてあることを推奨する程度では効力はありません。ただでさえ医療機関は経営難の問題を抱えています。なんらかの経済的な補助や強い行政指導がなければ、医療従事者ひとりの労力を輸血の監視だけにつけるのは無理です。
それは、医療費がかかるから困難だという議論が上がりそうですが、輸血の適正使用を推進し、無駄な輸血を減らすことだけで、医療費の削減や輸血事故の減少、輸血による感染症の発生率を押さえられるのです。
(輸血医療のノウハウを細胞治療の発展に生かす)
細胞治療とはヒトの組織を治療用として扱うものです。広い意味では輸血医療も細胞治療と言えます。輸血用血液の管理体制のノウハウは、細胞治療のノウハウに合致しますので、永年、培ってきた輸血部門の技術を上手く活かすことができればいいと思います。
例えば、白血病の治療に応用されている造血幹細胞移植の場合、造血幹細胞には血液型以上にHLA(ヒト白血球抗原)というたくさんの型がありますので、まず型をきちっと調べることが必要です。また細胞は生ものですから、保存の温度管理は薬剤以上に厳格でなければなりません。
たとえば輸血に使う赤血球製剤は2~6℃で保管します。常温で放置すると酸素の運搬能力が落ちてしまうからです。造血幹細胞は凍結させて保管することがありますが、この場合も、間違えて不適切に溶かしてしまうと細胞が死んでしまいます。
ですから、保管している冷蔵庫が壊れたら大変なことになるのです。当院では輸血科の冷蔵庫の温度情報が守衛さんまでいくようになっており、夜間に冷蔵庫が故障したら、守衛さんから私の自宅に電話が入るようになっています。場合によっては、当院の近くの職員や守衛さんにお願いして予備の冷蔵庫に移してもらうこともあります。
なおかつ自動温度記録装置をつけて、庫内の一日の温度変化を毎日チェックしています。さらに、毎朝職員が庫内の温度計の実測値を記録しています。
このように非常に厳格な温度管理を行なっています。
臍帯血移植や骨髄移植などの造血幹細胞の管理も輸血部門が支え、共通のノウハウを活かすことができれば効率が良いでしょう。それにより、輸血部門を整備する意義も高まると思います。
(高度な専門性にふさわしい整備を)
輸血はこの10年間で大きく進歩し、高度な専門性のある医療行為になってきました。そのため、ソフト面でもハード面でも専門的に整備しなおさないと、安全性を確保できないということを強調したいです。血液製剤の適正使用をすすめるにおいても、専門的な人員の配置と専門的な部署の整備が必要不可欠だと思います。それができない医療機関では、患者さんの安全確保のために輸血を行なうことはやめた方がいいでしょう。
輸血のリスクは世間を騒がせているウィルス感染だけではない。自己血輸血のリスクも十分認識しておきたい。使用過剰も不要なリスクの増加をもたらす。
これだけリスクの多い部門にも関わらず、使用基準や監視体制が周知徹底されていないというのには驚いた。まずは輸血部門を整備する、国を挙げての協力体制が急務であろう。