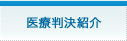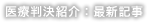東京高等裁判所平成6年1月24日 判例タイムズ873号204頁
(争点)
医師に注意義務違反(速中性子線治療を継続すべきでないのにこれを継続した注意義務違反)があったか否か
*以下、原告を◇、被告を△と表記する。
(事案)
◇(昭和57年当時42歳)は、昭和55年4月21日、5、6年前から右頸部にリンパ節腫脹がある旨の開業医の紹介状を持参して、国である△の開設するT大学医学部附属病院(以下「△本院」という。)の耳鼻咽喉科腫瘍外来を受診し、I医師ら3人の同科腫瘍外来担当医による病歴、経過等の問診、視診、触診を受け、かつ血液検査、心電図検査等の指示を受けた。
問診による病歴、経過は、3年以上前から右耳下部に腫瘤が発生し、徐々に数が増えてきた、自発痛はなく、圧痛がある、日によって硬さに変化があり、体重は変化がないというものであった。
視診、触診の結果によると、右頸部の側方に耳介下部から鎖骨上窩まで副神経リンパ節群の腫脹が5個あり、耳介下部に一番近いものが最も大きく41ミリ×24ミリで、胸鎖乳突筋の後上部に位置し、残りはそれぞれ12ミリ程度から20ミリ程度の大きさであった。また、下顎骨体の下縁に沿って、20ないし30ミリ程度の大きさのリンパ節腫脹が1個認められた。
I医師は、これらの腫脹につき、互いに癒着せず、腫瘤の硬さは、一様にカマボコの硬さ、すなわち弾性を有するが波動は触れず充実性が認められる、耳下部最上部の腫脹は基底部との癒着があり可動性を欠いたが、その他は可動性が保たれていた、皮膚との癒着は全腫瘤に認められないと診断し、これと上記診察結果を総合して検討の上、悪性腫瘍と判断した。そして急速な全身転移を来し易く極めて経過が悪いが放射線治療が有効なリンパ上皮腫又は悪性リンパ腫のいずれかであることが確実と診断した。
その上でI医師は、◇の腫脹の原発巣は上咽頭が最も疑われると考えたが、上咽頭の後上壁右寄りにわずかに隆起がみられるのみで、他に原発を思わせる所見は認められなかった。
そこで、I医師は、この部分について生検を実施することを考えたが、検査だけやってその結果を待っているというのでは危険なので、治療計画を立てそれとの組み合わせで生検を実施するという方針の下に、この隆起部分の生検を昭和55年4月28日に実施する予定を立てた上で、◇に対し、腫瘍の治療のため直ちに△の開設する△大学医科学研究所附属病院(以下「△医科研」という。)で診察を受けるよう指示した。
同月24日、◇は△医科研のK医師の診察を受けた。K医師は◇の腫脹を悪性腫瘍と診断し、速中性子線治療が妥当と考えて速中性子線担当のO医師を紹介した。
翌25日、O医師は◇を診察し、◇の右頸部の腫脹は、リンパ上皮癌が最も疑われると考えた。そして、同日、照射線量(腫瘍線量)を1回120ラド、週2回全12回を目標として、速中性子線による治療を開始した。その後、第6回の照射時である同年5月12日から照射野を縮小し、第11回照射時の同月30日からさらに照射野を縮小して、同年6月9日まで、当初予定していた12回より2回多い合計14回、腫瘍線量にして1680ラドの速中性子線治療を行った。なお、この治療では、速中性子線は脊髄にかかる方法で照射されていたものである。
一方、△本院の方でも経過観察が続けられ、昭和55年4月28日に上咽頭の隆起部分の生検が行われたが、同年5月2日に悪性でないという結果が出た。さらに、同年6月30日に中耳からも生検を行ったが、悪性との結果は出なかった。
昭和56年3月2日△医科研での診察の際、◇の左腋窩部に腫瘤が2個認められたので、O医師は肺への癌の転移を疑い、胸部レントゲン撮影を行ったが異常はなかった。同日、I医師も診察し、悪性腫瘍との疑いをもった。O医師は、さらに2回の経過観察の後、この腫瘤について生検を行うのが望ましい旨決定した。それを受けてI医師は、△本院第二外科に対し生検を依頼し、同月25日に△本院第二外科で左腋窩部及び右頸部の腫瘤(以下「本件腫瘤」という。)について生検が実施されたところ、本件腫瘤はいずれも結核性リンパ腺炎であるとの診断であった。そこで△本院第一内科において結核治療を行ったところ、その半年後に本件腫瘤は消失した。
昭和57年中頃より、◇に、排尿、排便困難や下半身のしびれ、下肢の筋力低下が出現し、昭和58年1月より△本院神経内科及び△本院泌尿器科の診察を経て、△医科研での速中性子線照射に起因する放射線性脊髄炎と診断された。
◇は、昭和59年2月より杖歩行となり、左右両側上下肢麻痺、膀胱直腸障害等の症状があり、身体障害者法別表掲記の第1級の身体障害者に認定されている。
そこで、◇は、△に対し、後遺障害が残ったことについて、△本院及び△医科研の医師らの過失に基づくものであり、医師らの使用者である△には不法行為に基づく責任があるとして損害賠償請求をした。
一審判決(東京地裁平成4年4月10日)は、◇の請求全額を認容し、それを不服として△が控訴した。
(損害賠償請求)
- 患者の請求額:
- 1億4141万7800円
(内訳:一審裁判所の認容額が患者の請求額と同額なので、内訳も一審裁判所認容額の内訳と一致すると推測される)
- 一審裁判所の認容額:
- 1億4141万7800円
(内訳:付添費2659万6838円+逸失利益8894万2374円+慰謝料2000万円+弁護士費用1000万円の内金)
控訴審裁判所の認容額
- 認容額:
- 1億4141万7800円
- 内訳:
- 一審判決を引用
(控訴審裁判所の判断)
医師に注意義務違反(速中性子線治療を継続すべきでないのにこれを継続した注意義務違反)があったか否か
この点について、裁判所は、I医師としては、自ら原発巣として最も疑いを持った上咽頭の隆起についての生検の結果が悪性ではないという重要な内容を示すものであったのであるから、少なくとも一つの可能性として、本件腫瘤が悪性でないことを考えるべきであったとしました。裁判所は、生検を実施した4月28日の時点では速中性子線の照射はまだ2回行われただけであったから、生検の対象となった上咽頭の原発巣が既に消滅していたという可能性はどちらかというと少なかったとみるべきでなかろうかと指摘しました。そして、同医師は悪性度の高い腫瘍に限って放射線の感受性は非常に高いので、1、2回照射しただけで消滅することはよく経験することであると述べているが、わざわざ生検を実施しておきながら、この程度の考えで生検の結果を重視しないままに終わったのは疑問であると判示しました。
裁判所は、速中性子線治療の評価が定まったものではなく、また正常組織に対し損傷を及ぼす危険性のあること(脊髄に当たる方法で照射した場合には、耐容線量内であっても、副作用が起こる可能性があることが認められる。)を考慮すると、連中性子線治療を継続すべきかどうかは、状況の変化に応じ検討を重ねるべきものであり、原発巣と疑われた部位について悪性ではないという生検の結果が出た5月2日までの間、速中性子線の照射は同日実施分を含めてまだ3回行われたにすぎないのであるから、この時点で照射を止めれば、正常組織に損傷を及ぼす危険性は少なく済んだと考えられ、したがって、その後も速中性子線治療を続行するかどうかについては慎重な考慮が必要であったと判示しました。
また、放射線の専門医であるO医師としては、放射線照射の依頼を受けた時点で近々生検を予定していることを知っていたのであるから、照射開始後においても絶えず生検の結果に関心を持ち、漫然と照射を継続することなく、本件腫瘤への速中性子線照射の継続が必要かつやむを得ないものであるかを確認し、正常な細胞への放射線損傷を最小限にとどめるべき業務上の注意義務があったと解すべきであると判示しました。
ところが、I医師は、速中性子線治療の開始後5月2日に悪性腫瘍ではないとの生検の結果が出ていたにもかかわらず、次回の診察日である5月8日になって初めてこれを知り、生検前2回の照射により癌細胞が消滅したことによるものであると即断し、その後他の原発巣を積極的に探索したり、疑わしい部位あるいは本件腫瘤については生検等を実施することなく、しかも5月26日にO医師から問い合わせを受けるまでこの生検の結果を同医師に伝えず漫然と速中性子線治療を継続するに任せたものであると指摘しました。
裁判所は、I医師は、当初放射線治療計画との組み合わせで上咽頭の生検を実施するという方針を立てており、生検の結果を考慮するという前提で、速中性子線治療を開始したとみられるのであり、照射回数が増えればそれだけ正常組織に対する損傷の可能性を増すのであるから、生検の結果については絶えず関心を払い、次回の診療日を待たずとも、生検の結果が出れば直ちにこれを確認しその後の治療計画を検討すべきであった(大学病院その他の大病院においては、カルテの保管、整理等の関係上、次回の診察日に出されたカルテを見て初めて担当医が検査結果を知るというのが常態であるかもしれないが、次回の診察日を待たずに検査結果を知ることは、医師がそのつもりになれば可能であり、そのことを要求することは、決して実情を無視したものではないと考えられる。)。I医師はこのような対応を怠り、漫然と速中性子線治療を継続するに任せたのであるから、この点において注意義務の違反があったといわなければならないとしました。
裁判所は、またO医師は、4月25日に速中性子線治療を開始するに先立ってI医師から同月28日に生検を実施する予定であることを知らされていながら、5月26日に問い合わせてその結果を知らされるまで約1ヵ月の間、漫然と照射を継続し、10回の照射を行ったのであるが、O医師としてもやはり生検の結果については絶えず関心を払い、I医師から連絡がなければ自分の方から問い合わせて結果を確認し、検査結果の如何によっては速中性子線の照射を中止することも含めて照射計画を再検討すべきだったと考えられると判示しました。
このように心がけていれば、O医師は生検の結果が出た5月2日の直後の時点で悪性ではないとの検査結果を知ることができたはずであり、O医師においてこれをしないで照射を継続したことは、注意義務を尽くさなかったといわなければならないとしました。
なお、速中性子線治療は一旦開始した以上中断、中止するのは望ましくないとされているが、それは主として治療効果の持続性等からする配慮であるとみられるのであって、上記の状況においてさえ中断、中止すべきではないとの要請があるとは考えられないとしました。
裁判所は、I医師及びK医師、O医師らにおいて、速中性子線治療を開始した時点における判断としては、直ちに注意義務違反があったとはいえないが、生検の結果が出た後においては、治療を継続すべきではないにもかかわらずこれを継続して実施した点において、医師としての注意義務違反があったと判断しました。
裁判所は、以上から、△の控訴を棄却し、その後判決は確定しました。