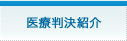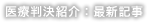東京地方裁判所平成7年9月22日判決 判例タイムズ916号192頁
(争点)
放射線治療の方法に過失があるか否か
*以下、原告2名をあわせて◇ら、被告を△と表記する。
(事案)
A(昭和7年生まれの主婦)は、昭和59年5月22日国である△の設置・経営する病院(以下「△病院」という。)で検査を受けたところ、胸部X線写真と同断層写真から左肺下葉の無気肺が認められたため、同月30日、検査のための入院を勧められ、同年6月6日△病院に入院し、Aと△との間で、検査及び治療を目的とする診療契約が成立した。
Aは、入院後の同月12日、気管支ファイバースコープ検査により左主気管支に原発した腫瘍が気管にまで浸潤していることが発見され、病理組織検査(生検)により腺様嚢胞癌であると診断された。同月15日には、胸部CT検査により気管及び左主気管支の内外に腫瘍が形成されていることが発見された。
肺の腺様嚢胞癌は、気道(気管、気管支)の粘膜上皮から発生して、気管支上皮下を這うように進展し、気管支全体をやや長い範囲にわたって狭窄、閉塞する特徴があり、Aの場合も、癌が左主気管支から気管という気道部分に発生して、高度の狭窄が認められたため、気道閉塞の危険があった。
そこで、同月16日、△病院外科のN医師によって、気管管状切除及び左肺全摘除、リンパ節郭清術の手術が施された。しかし、Aの右肺が全面的に癒着して、その癒着剥離に時間がかかり、手術途中で低酸素血症が著明となったため、手術を中止せざるを得なくなり、手術は試験開胸に終わった。
Aは、その後も左主気管支狭窄による呼吸困難が続き、左肺の機能がほとんどなくなり、このまま放置すると左主気管支だけでなく、右主気管支も閉塞して窒息死する危険性があったことから、早急にこの状態を改善させる必要があったため、N医師は、その方法として放射線治療を検討し、Aの夫にこの治療の説明をした。
そして、同年11月15日から同年12月21日までの間、△病院放射線科S医師によって、左主気管支から気管支にかけて、照射野を8×8センチメートルとして、前後対向二門照射の方法により、1回2グレイを週5回(合計54グレイ)照射する放射線治療が施された(以下「1回目の放射線治療」という。)。
1回目の放射線治療により、Aの呼吸困難等の症状は軽快し、腫瘍も縮小して、左主気管支の閉塞も軽減した。しかし、同月25日に実施された気管支ファイバースコープ検査及び生検により左主気管支に癌の遺残が認められ、これを放置すれば癌の再増殖により、気管閉塞から窒息死に至る危険が明白であったため、放射線の追加照射が決定された。
そして、昭和60年1月10日から同月19日までの間、S医師によって、同部位に照射野を6×6センチメートルとして、前後対向二門照射の方法により、1回2グレイを週5回(合計14グレイ)照射する放射線治療が施された(以下「2回目の放射線治療」という。)。
2回目の放射線治療後、腫瘍はさらに縮小したものの、気管支ファイバースコープ検査ではまだ癌が残っているのが認められた。しかし、S医師は、これ以上の放射線治療は副作用を考えると不可能であったことから、Aを退院させて経過観察を行うこととし、同年3月17日、Aは△病院を退院した。
同年4月11日、Aは、心部から左胸部にかけての痛みが出現し、下痢も併発したので、同月13日、△病院に再入院したところ、胃体上部小弯に小潰瘍が発見され、委縮性胃炎の症状が認められた。また、気管支ファイバースコープ検査の結果、左主気管支膜様部粘膜面に不整が認められ、生検では癌細胞陰性であったが、ファイバースコープによるブラッシングでは腺様嚢胞癌が認められた。しかし、経過観察をすることとされ、投薬により上腹部の症状がとれたため、Aは退院した。
その後、Aは、同年5月24日から同年7月12日まで、同年8月23日から同年12月13日まで、昭和61年2月7日から同年7月4日まで、いずれも△病院呼吸器外科外来に通院して検査を受け、また、昭和60年7月27日、昭和61年1月11日及び同年3月7日には、いずれも△病院に検査目的で入院したが、胸部Ⅹ線写真撮影や気管支ファイバースコープ等の検査によっても異常は認められなかった。
ところが、Aは、同年8月2日、胃及び気管支の検査のため△病院に再入院し、同月8日、気管支ファイバースコープ検査を受けたところ、気管分岐部から口側へ3リングの部分から5リングの高さまで気管膜様部側に腫瘤病変及び表面の粘膜下毛細血管の怒張が認められた。これは、これまでに放射線治療を施した範囲外の部位の肺癌の再発であると考えられたため、同月13日から同年9月17日までの間、この部位に、照射野を縦4センチメートル、横5センチメートルとして、斜入対向四門照射の方法により、1回2グレイを週5回(合計50グレイ)照射する放射線治療が施された(以下「3回目の放射線治療」という。)。
3回目の放射線治療の結果、病変はほぼ消失し、Aは同月28日に△病院を退院し、その後△病院の外来で経過観察を受けていたが、同年12月20日ころから、胸部疼痛が増強して、左下肢の痺れ感が現れ、昭和62年1月16日には、両下肢痛が増強して、左下肢が動かなくなり、同月20日には左胸痛及び左脚痺れ感が著しく、歩行困難となったため、同月21日に△病院に再入院したものの、入院時には第6胸椎以下の不全麻痺があり、胸部側面X線写真の結果、第6胸椎に圧迫骨折が認められ、骨シンチグラムの検査において、第6胸椎に集積像が見られた。N医師は、この時点では、疼痛も強く、癌の骨転移による不全麻痺及び疼痛の疑いが最も強いものと考えて、放射線治療が必要であると判断した。
そこで、同年2月5日から、第6胸椎に対して、照射野を4×4センチメートルとして、一二門照射の方法により、1回2.4グレイの放射線治療が開始された。しかし、両下肢ともに完全麻痺となり、疼痛の緩和等の臨床的効果もなかったため、S医師の判断により、同月12日に合計12グレイを照射したところ、放射線治療は中止された。
その後、Aは第6胸椎以下の完全麻痺の症状が固定し、回復不能と判断され、同年6月10日に△病院を退院し、国立療養所H病院へ転院して、リハビリテーションの治療を受けたが、平成4年10月3日、死亡した。
Aの第6胸椎以下の完全麻痺の症状は、上記放射線治療の副作用としての放射線脊髄症によるものであり、1回目及び2回目の放射線治療において、前後対向二門照射の方法で合計68グレイの放射線を照射された際に、第6胸椎も同量の放射線を被曝したことから放射線脊髄症が発症し、その後第6胸椎以下の完全麻痺の状態となった。また、死亡の原因は、放射線脊髄症による慢性呼吸障害から生じた肺炎である。
そこで、生前Aが訴訟を提起し、死亡後はAの相続人(子)である◇らが訴訟を承継して、Aが放射線脊髄症となり、死亡したのは、△病院の担当医師らに過失があるからだとして、△に対して、診療契約の債務不履行に基づく損害賠償を請求した。
(損害賠償請求)
- 請求額:
- 患者遺族2名合計6625万円
(内訳:慰謝料3000万円+逸失利益2880万円+介護費用及び雑費1500万円+弁護士費用738万円の合計8118万円の内金)
(裁判所の認容額)
- 認容額:
- 患者遺族2名合計4251万8240円
(内訳:慰謝料2000万円の7割1400万円+逸失利益1421万8241円(逸失利益として算出された額の7割から障害基礎年金及び障害厚生年金を控除した残額)+介護費用及び雑費1500万円の7割1050万円+弁護士費用380万円。相続人が複数のため端数不一致) - *放射線治療による癌の完治率が2割程度であることや患者の病状から適切な照射方法で、かつ照射量を肺の耐容線量以下に抑えたとしても、放射性肺炎等の障害が発症する可能性も残されていることから、患者が完治することを前提に損害額を算定するのではなく、慰謝料、逸失利益、介護費用及び雑費については、合計額の7割をもって本件放射線治療と相当因果関係のある損害と認定
(裁判所の判断)
放射線治療の方法に過失があるか否か
この点について、裁判所は、まず、放射線脊髄症は、一旦発症すると有効な治療法がなく、その変化は不可逆性であり、日常生活に支障を来し、生命に関わる重度の障害となり、ほとんどの場合が死に至るものであることが認められる。したがって、放射線治療を行う者は、放射線部位に脊髄が含まれる場合には、できるだけ脊髄への照射を回避する措置を採り、その耐容線量を超えないようにする注意義務を負うものというべきであると判示しました。
そして、1回目及び2回目の放射線治療は、前後対向照射の方法により合計68グレイの放射線を照射しているが、この方法では脊髄が病巣部位と同量の放射線を被曝することとなり、脊髄にも合計68グレイの放射線が照射されたことになると指摘しました。
裁判所は、脊髄の耐容線量は、個体差があり、また照射野や1回の照射線量によっても異なるものであって、単純に決められるものではないが、1回の照射量が2グレイ程度であり、照射野が広くない場合の脊髄の耐容線量は、大体40から50位の間であること、本件の放射線治療当時教科書的扱いを受けていた「癌・放射線療法」にも脊髄の耐容線量は45グレイであるとの記載があり、これが当時の標準的な考え方であったこと、また、同年の米国対癌協会の放射線治療マニュアルには、放射線脊髄症の最低認容線量(5年以内に1ないし5%の確率で障害を起こす線量) は45グレイ、最大耐容線量(5年以内に25ないし50%の確率で障害を起こす線量) は 55グレイである旨、1979年出版の外国の放射線治療の教科書には、脊髄照射は45グレイ/4週を超えてはならない旨それぞれ記載されていること、脊髄に68グレイの放射線が照射された場合には、放射線脊髄症発生の危険性が非常に高いこと、以上の事実が認められるとしました。
裁判所は、したがって、1回目及び2回目の放射線治療により照射した合計68グレイの放射線は、脊髄の耐容線量を超え、放射線脊髄症発生の危険性の高い線量であることが認められると判断しました。
さらに、脊髄への照射を回避する方法としては、斜方向からの照射法、回転照射法、多門照射法等があるが、本件においても、斜方向からの照射野を設定して、病巣部位のみを照射することは技術的に可能であり、実際、△病院で行われた3回目の放射線治療において採用された斜入対向四門照射の方法によれば、脊髄への照射を避けられたものと認められ、△病院の担当医師は、本件の病巣部位への照射線量を維持して、しかも、脊髄への照射を回避する措置を採り得たものと認められるとしました。
裁判所は、放射線脊髄症が有効な治療方法がなく、その進行が不可逆的で、死に至る危険性の極めて高い病気であることに鑑みると、脊髄への放射線被曝が余儀なくされるときには、その耐容線量を超えないように、厳格な注意義務が要求されるものといわなければならないところ、△が1回目及び2回目の放射線治療により前後対向二門照射の方法で照射した合計68グレイの照射量は、放射線脊髄症発生の危険性の高い線量であること、本件診療等時、本件の病巣部及びその周辺を含めた必要とされる照射部に同量の放射線量を照射する場合でも、脊髄への放射線照射を回避し、かつ、放射線肺炎を防ぐ照射方法が存在し、その方法を採用することも可能であったこと、その他諸事情を総合すると、△病院の担当医の実施した1回目及び2回目の放射線治療の方法は、少なくとも脊髄への放射線照射を回避すべきであるのに、その措置を怠ったものといわざるを得ないとして、△病院の担当医師に、1回目及び2回目の放射線治療についての過失を認定しました。
以上から、裁判所は、上記(裁判所の認容額)の範囲で◇らの請求を認め、この判決に対して控訴がなされましたが、控訴審で和解が成立して訴訟は終了しました。