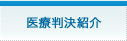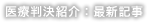東京高等裁判所平成30年9月12日判決 判例時報2426号32頁
(争点)
- 褥瘡発生を防止すべき義務を怠った過失の有無
- 6月20日の初回の褥瘡回診後、褥瘡を適切に治療すべき義務を怠った過失の有無
*以下、原告を◇、被告を△と表記する。
(事案)
A(昭和10年生まれの男性。平成25年6月20日当時77歳)は、平成22年2月頃から前立腺がんの治療のためH病院に通院していた。Aは、同年9月28日に歩行障害のためI病院を受診し、同年11月17日から精査のため入院し、大脳皮質基底核変性症と診断された。Aは、同年12月4日に退院して自宅療養しており、平成24年7月2日から要介護5であると認定された。
Aは、平成25年(以下の日付は、特に断りのない限り、同年のものである。)2月9日からJ病院に入院し、誤嚥性肺炎、大脳皮質基底核症候群と診断された。
Aは、3月15日、リハビリ等のため医療法人である△の運営する病院(以下「△病院」という。)に転院した。
Aは、5月27日、低栄養状態を改善するために胃ろう造設術を受けた。Aは、同日以降、△病院の4階(術後管理を要する患者や長期入院や終末医療の患者を対象とする。)に移動した。Aは、5月28日時点で身長165cm、体重43.6kg、BMI16.0であった。
Aは、遅くとも6月18日までに、△病院の看護師により、仙骨部に発赤があることが確認された。Aは、6月20日の褥瘡回診の際に、△病院のP医師により仙骨部に第Ⅱ度の褥瘡があることが確認された。
Aは、8月9日、仙骨部褥瘡の治療等のため、K病院に転院した。Aは、平成26年2月17日、仙骨部褥瘡の治療のためL病院に転院した。Aは、同年3月18日、仙骨部褥瘡の手術のためM病院に転院したものの、全身状態が悪かったため、手術は断念された。
Aは、同年7月31日、終末期医療を受けるためN病院に転院した。Aは同年11月4日、敗血症により死亡した。
そこで、Aの長女◇は、Aがその死亡までの間複数の医療機関で褥瘡の治療を余儀なくされたのは、△病院の医療従事者が褥瘡の予防及び適切な治療を怠ったためであると主張して、△に対し、債務不履行に基づく損害賠償請求をした。
原審が請求を一部認容したところ、これを不服とした△が控訴した。
(損害賠償請求)
- 患者遺族の請求額:
- 2066万2588円
(内訳:治療関係費325万1680円+カルテ開示費用2万5155円+付添費用326万9500円+付添交通費23万7836円+慰謝料1200万円+弁護士費用187万8417円)
(原審及び控訴審裁判所の認容額)
- 認容額:
- 668万2956円
(内訳:治療関係費192万9860円+カルテ開示費用2万5155円+付添費用98万8325円+付添交通費3万9616円+慰謝料310万円+弁護士費用60万円)
(控訴審裁判所の判断)
1 褥瘡発生を防止すべき義務を怠った過失の有無
この点について、控訴審裁判所も、以下の原判決を引用して原審同様に△に過失があると認定しました。
△は、Aが、平成25年6月頃77歳と高齢であり、同年5月27日に胃ろう造設術を行うなど低栄養状態であったこと、この頃BMIが16.0と痩せていたこと、大脳皮質基底核変性症であったことなど褥瘡発生のリスクが高い患者であること及び△病院の医療従事者がAに褥瘡が発生することを予防するための対策を行うべき一般的義務を認めている。以上に加え、△病院におけるAの褥瘡管理が、ガイドライン、看護計画及び院内マニュアル等に基づくことからすれば、△病院の医療従事者は、Aに対し、体位交換を最低2時間ごとに実施する、体圧分散寝具を使用する、皮膚に異常がないか観察する(異常がある場合にそれが褥瘡であるか否かを鑑別することを含む。)といった義務を負うものと認める。
そして、Aが△病院の4階に移転した5月27日から7月10日まで通常のマットレスが使用され、体圧分散マットレスが使用されていなかったこと、そのような状態で、△病院の医療従事者が、2時間ごとの体位交換を遵守していたとは認められない(診療録等には体位交換をいつ行ったかの記載はなく、本件全証拠によっても、△病院において体位交換表に記載された頻度で体位交換を行うことについて、体位交換を実施した時間を記録するなど看護師間で情報を共有する具体的な仕組みや運用があったとは認められない。)ことは、上記義務に違反する。
したがって、△病院の医療従事者が2時間ごとの体位交換を実施せず、5月27日から褥瘡発生を認識した6月20日まで通常のマットレスを使用した点で、Aの褥瘡発生を防止すべき義務を怠ったと認められる。
6月18日から6月20日までの間に、△病院の医療従事者が、Aの仙骨部の発赤について鑑別及び経過観察をすべき義務を怠った過失も認められる。
2 6月20日の初回の褥瘡回診後、褥瘡を適切に治療すべき義務を怠った過失の有無
この点について、控訴審裁判所も、以下の原判決を引用して原審同様に△に過失があると認定しました。
- (1)
-
体圧分散寝具は、褥瘡の悪化を防止するためにも必要かつ効果的であるから、△病院の医療従事者は、褥瘡の治療に当たり、体圧分散寝具の有無・用法等を検討する義務を負う。
しかるに、△病院の医療従事者は、6月20日に褥瘡を認識した後も7月10日まで通常のマットレスを使用し、かつ、6月20日以降褥瘡が悪化しているにもかかわらず、7月12日のカンファレンスまで体圧分散寝具について、カンファレンスで検討を行った形跡も、医師や看護師から低反発マットレスやエアマットレスを使用すべき旨の指示があるなどの事情も見られない。したがって、7月11日にAの家族が指摘するまでエアマットレスの使用を検討していない点につき、△病院の医療従事者に過失があると認められる。
- (2)
-
医療従事者は、褥瘡のステージや病態(壊死の深度や感染の程度等)を正確に判断した上で、当該褥瘡に応じた適切な治療等を行う必要がある。そして、院内マニュアルにはデブリードマンの実施や褥瘡感染についての言及がある以上、Ⅱ度以上の褥瘡に対する治療方法を個別に規定していないことを考慮しても、△病院の医療従事者は、褥瘡のステージを正確に判断することはもちろん、細菌検査や創培養といった感染の評価をすべき義務や、デブリードマンを徹底する義務を負う。
7月18日、8月1日及び8月5日の褥瘡は、筋肉及び臓器に達している以上、ステージとしてはⅢ度以上であると認められる。そうすると、いずれの褥瘡もⅡ度であると判断した医師は、そもそも褥瘡のステージの評価を誤っている以上、△病院の医療従事者がおよそ褥瘡の病態の評価、褥瘡に応じた適切な治療等を実施したとは認められない。そして、Aは6月20日以降ほぼ毎日発熱があり、7月4日以降は褥瘡回診のたびに局所の明らかな感染徴候ありと評価されているのであるから、△病院の医療従事者が、6月20日以降に細菌検査を行わなかったことや7月4日以降に創培養をしなかったことは正当化できない。また、7月4日には黒色壊死の部分と一部肉芽が形成されている部分があることが認められ、これは局所感染と判断される症状であるから、壊死組織の除去(デブリードマン)を行う必要があったのに、医師は同月18日までデブリードマンを実施しなかったのであり、その処置が適切であったとは言い難い。
したがって、細菌検査及び創培養を行わなかったこと、7月4日に黒色壊死や一部肉芽があるにもかかわらず同月18日までデブリードマンを実施しなかった点についても△病院の医療従事者に過失があると認められる。
- (3)
以上により、6月20日の初回の褥瘡回診後、褥瘡を適切に治療すべき義務を怠った過失を認める。
以上から、控訴審裁判所は、上記(原審及び控訴審裁判所の認容額)の範囲で◇の請求を認めました。