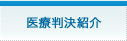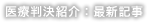今回は、放射線治療に関して、医師の過失が認められた裁判例を2件ご紹介します。
No.530の紹介にあたっては、一審判決(東京地裁平成4年4月10日判決)も参考にしました。
No.530の事案では、耳鼻咽喉科の医師が、患者の頸部腫脹を悪性腫瘍と判断し、放射線照射が必要であると考え、放射線科に治療を依頼し、放射線科の医師は速中性子線照射による治療を採用して実施しました。裁判所は、医師が当該疾患につき臨床所見によって悪性腫瘍の疑いをもった場合は、可能な限り各種の検査方法を駆使して真実悪性腫瘍であるかどうかを解明し、その結果に基づき適切な治療を実施すべき注意義務があると解され、当該腫瘍が転移性とみられる場合には、原則として原発巣の発見に努め、可能な限り生検等の方法により病理学的に診断を確定することが要求されると考えられると判示し、また、放射線科の医師は、他の科の医師から依頼を受けた場合、依頼者である医師との間で、当該疾患が悪性腫瘍であるか、その疑いがどの程度確実なものであるか、その治療に放射線治療が適しているか、どのような放射線を照射するのがよいか等につき十分協議をして、当該患者に適切な治療が行われるようにするとともに、不必要な放射線の照射が行われて正常な細胞が損傷を受け重要な結果を生ずることがないように、可能な限り配慮する注意義務があると判示しました。
No.531の事案では、病院側は、1回目の放射線治療は、気道閉塞による窒息死を回避し、呼吸機能を温存するために、病巣部位に確実に照射できて短時間に治療が済み、かつ、肺への照射を避けることのできる前後対向二門照射の方法を採用したのであり、また、2回目の放射線治療も、癌の残存が認められたことから、窒息死を回避し、呼吸機能を温存するために、右主気管支をできるだけ照射野に含め、しかも右肺を照射野から外すことのできる前後対向二門照射の方法を採用したのであるから、その方法により、脊髄に耐容線量以上の放射線が照射されたとしてもやむを得ないと主張しました。
しかし、裁判所は、脊髄の耐容線量を超えるような放射線照射をする場合には、その耐容線量を超える時点までには、既に病巣部位に対してある程度の放射線が照射されており、呼吸困難も一応収まっていると推認できるし、被告病院が斜入対向四門照射の方法を採用し、これを実施することは技術的に可能であることからすると、最後まで前後対向二門照射の方法で行う必要はなく、遅くとも耐容線量を超える時点では、前後対向二門照射の方法以外の照射方法を採用すべきであったといえると判断して、病院側の主張を採用しませんでした。
両事案とも実務の参考になるかと存じます。