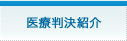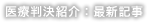横浜地方裁判所平成24年3月23日判決 判例時報2160号51頁
(争点)
入所者の褥瘡の悪化に関して老人ホーム側に債務不履行・注意義務違反があるか否か
*以下、原告を◇1ないし◇4、被告を△と表記する。
(事案)
A(大正7年生まれ・死亡当時87歳の男性)は、平成3年以降、糖尿病にり患しており、平成4年頃には大腸がんの手術を受けた。そのほか、遅くとも平成11年以降、高血圧症、出血性直腸憩室炎、脳梗塞後遺症、肺炎、胆嚢炎、尿路感染症、前立線肥大、慢性腎不全、高尿酸血症等の既往歴を有し、病院への入退院を繰り返していた。
また、平成11年9月からは、自宅にいる間、K訪問看護ステーションからの訪問看護を受け、平成16年頃からの看護の内容は、症状観察、清潔援助、褥瘡処置、リハビリ、排せつ援助等であった。
平成17年1月25日には、Aは介護保険制度における要介護4の認定を受けていた。
平成17年8月、Aは、肺炎によりY病院に入院し、退院後、入院中の転倒が原因で背部痛を訴えたことから、同年9月7日、N病院を受診し、腰椎圧迫骨折と診断され、そのまま入院した。
Aは、入院時、尿路感染症にもり患しており、同月18日には、敗血症の寸前にまで至り、急変時の対応が定められたほどであったが、加療により症状が改善した。その後も、上部消化管からの出血の疑いや胸水の増加があったものの、同年12月14日、N病院を退院した。
N病院の担当医であったH医師は、同月12日付け「紹介・診療情報提供書」に、今回入院時の病状経過を記載するとともに、完全にCRP値(C反応性蛋白。体内で炎症反応が起きているときに血中に現れる。)及びWBC値(白血球数)を陰性化することは困難と思われる旨記載した。
また、Aは、N病院を退院する以前に、仙骨部及び両足踵部に、褥瘡(運動低下、知覚障害、骨突出等が原因で、身体の一部に持続的な圧迫が加わることにより、皮下の血流が低下又は停止され、皮膚及び皮下組織が阻血性障害に陥り生じる皮膚潰瘍)を生じており、退院時において、仙骨部の褥瘡(以下「本件褥瘡」という。)の大きさは、直径3cm程度であった。なお、仙骨部は、褥瘡の好発部位である。
Aは、平成17年12月14日、N病院を退院後、自宅において、妻である◇1とK訪問看護ステーションから派遣されるヘルパーによって、24時間態勢の介護を受けて生活していた。医療については、従前からかかりつけであったH内科クリニックのT医師の診察を受けていた。
T医師は、同月17日の診察で本件褥瘡を確認し、治療薬として抗生物質であるダラシン錠(150mg)朝夕各1錠と外用感染治療剤であるゲーベンクリームを処方した。
Aと◇1の子である◇2は、AがN病院に入院しているときから、◇1にAの介護の負担がかかっていると考え、Aの介護施設入所を検討し、その後◇1は自宅での介護に不安を持つようになったことから、Aを有料老人ホームの設置経営等を目的とする株式会社である△の経営する介護付き有料老人ホーム(以下「△施設」という。)に入居させることとした。
T医師が同月中に行ったAの血液検査の結果では、CRPは1.89(同月19日)、WBCは10200(同月27日)であった。
T医師は、診療録の同日欄に、「褥瘡は抗生物質にて改善している」と記載している。
Aは、平成17年12月29日、△施設に体験入居し、引き続き、平成18年1月4日に正式入居した。
Aは、△施設で、一日のほとんどをベッドに寝た状態で過ごし、体調が良いときには、車いすに移って、食堂で食事をとることなどもあった。排便には、おむつを使用し、排尿にバルーンカテーテルを使用していた。
平成17年12月29日から平成18年1月16日までの間、△施設の介護職員及び看護師は、Aについて、おおむね2時間ごとの体位変換を行い、T医師から処方されていたダラシン錠(150mg)を朝夕各1錠服用させた。
Aが△施設に体験入居した時点で、本件褥瘡には、商品名「コムフィール」というハイドロゲル創傷被覆・保護材(皮膚粘着面に配置された親水性コロイド粒子が滲出液を吸収して創傷部に湿潤な状態を作ることにより、組織の再生を促して治療を促進するとともに、外側面のポリウレタンフォームが、防水、外部刺激からのクッション、細菌感染・失禁汚染防止等の役目を果たすもの)が貼られていた。
△施設の看護師は、K訪問看護ステーションの「看護情報提供書」にあるとおり、これを3、4日おきに交換することとし、平成18年1月4日(以下、特段の断りのない限り同年のこととする。)、本件褥瘡に貼られていたコムフィールをはがして、これと同様のハイドロゲル創傷被覆・保護材である商品名「デュオアクティブ」に貼り替えた。なお、デュオアクティブは、外側面が肌色であり、一枚当たりの大きさが10cm×10cmであるところ、当日は、これを四分の一(5cm×5cm)程度の大きさに切って、貼り替えに使用した。
前日の同月3日には、T医師が、Aの状態を診るために△施設を訪れたが、本件褥瘡に悪化がないことを確認した。
△施設の看護師は、同月8日にも、本件褥瘡に貼られていたデュオアクティブを貼り替えた。その際も、一枚の四分の一程度を貼り替えに使用した。
本件褥瘡は、少なくとも同日頃までは、悪化している様子は見られなかった。
Aは、1月10日午前9時の時点で、体温が37.5度に上昇しており、熱感が認められた。△施設の看護師は、Aに対し、クーリングを行ったが、Aの体温は、同日午後4時の時点では、38.6度に上昇した。
△施設の看護師は、同日午後6時頃、Aの発熱を、△施設の協力医療機関であったS診療所の医師に電話で報告し、電話に出た医師から、体温が38度以上のときはロキソニン(解熱鎮痛剤)を投与するようにとの指示を受けた。看護師は、Aに対し、夕食後にロキソニンを投与した。
ロキソニンの投与により、Aの体温は、1月11日午前1時の時点で36.9度、午前6時の時点で36.6度と低下した。
しかし、午後になると、午後4時の時点で37.1度、午後8時の時点で38.0度と上昇し、翌12日午前6時には38.6度となった。
△施設の看護師は、1月11日午後5時頃、Aの排便が多量であることを確認し、本件褥瘡を処置した上、デュオアクティブを貼り替えた。その際も、一枚の四分の一程度を貼り替えに使用した。
Aの体温は、1月12日午前9時40分の時点でいったん37.4度まで低下した。
しかし、同日午後3時の時点で39.0度、午後5時の時点で38.9度と再び上昇した。
△施設の看護師は、同月10日の医師からの指示に基づき、ロキソニン投与を継続していたが、同日午後5時、S診療所のI医師に電話をかけ、午後6時、I医師と連絡が取れ、I医師から、ロキソニンとフロモックス(抗生物質)を投与するようにとの指示を受けた。
看護師は、Aに対し、ロキソニン及びフロモックスを投与し、その結果、Aの体温は、同日午後8時15分の時点で37.0度となった。
Aの体温は、1月13日は、36度台で安定し、その後16日まで、一時37度台前半になったことはあったものの、大半は36度台を保っていた。
一方、Aの尿量は、1月12日以降、一日あたり500mlに減少した。△施設の看護師は、Aに対し、頻回にミルキングを行うとともに、水分補給を促したが、状態は改善しなかった。
1月14日午前10時頃、△施設の看護師は、Aの仙骨部に便汚染を認め、仙骨部を洗浄した後、本件褥瘡に貼られたデュオアクティブを貼り替えた。
1月16日、I医師は、往診のため、△施設を訪れ、午前10時30分頃、Aを診察した。
I医師は、概ね1週間に1回、往診のため△施設を訪れ、各入居者について、2週間に1回診察を行っていた。年末年始の休診日を挟み、平成18年の年明け最初の往診は、1月16日と予定されており、△施設の職員は、◇らに対し、Aの入居前に、施設協力医の年明けの往診は同日となることを伝えていた。
往診前に行われたバイタルチェックによれば、Aの状態は、血圧が135/82、脈拍が79、体温が36.2度であった。また、△施設の看護師は、I医師に対し、Aの尿量が減少していることを報告した。
I医師は、Aのバルーンを交換し、踵の褥瘡の処置をし、足底を洗浄した。
本件褥瘡には、デュオアクティブ1枚が、そのままの大きさ(10cm×10cm)で貼られていた。I医師は、「デュオアクティブのようなドレッシング材は、患部に特に異常がない限り、1週間くらいははがさないでおく治療法である」と考えたことから、本件褥瘡に貼られたデュオアクティブをはがさずに、その上から本件褥瘡を観察し、特に異常はないと判断した。
同日午後2時50分頃、◇1と◇3(Aと◇1との間の子)が△施設を訪れてAと面会した。
◇1は、Aの状態を診て、「元気がなく、状態も悪化しているような気がする」などと述べた。I医師は、これに対し、「△施設では医療的なことはできず、Aの状態を改善するには病院に行く必要がある」などと答えた。
このため、◇らは、AをN病院に連れていくこととし、Aは、救急車でN病院に搬送された。
Aは、1月16日午後4時35分頃、N病院の救急外来を受診し、H医師が診察を担当した。午後4時42分時点のAの状態は、血圧が99/52、脈拍が83、体温が36.0度であり、声掛けに対する反応は乏しかった。
午後5時頃、Aに対するCT胸腹部単純撮影が行われ、H医師は、午後5時32分頃、N病院の画像診断部の医師から報告を受け、同じ午後5時32分頃、Aの血液検査の結果(CRPが27.22、WBCが24400)が報告された。
H医師は、これらの結果から、Aにつき、敗血症(循環血液を介して細菌やその毒素が広がることによる全身性炎症反応)を疑い、Aに対し、抗生物質や免疫グロブリン製剤の投与等の感染症の治療を実施することとした。
H医師が、本件褥瘡に貼られたデュオアクティブをはがしてみると、悪臭があり、汚染が著明であった。このため、H医師は、本件褥瘡の処置をした。
Aは、同日午後6時15分頃、N病院に入院した。入院時、褥瘡からの悪臭が強く、呼吸問題が一番の問題とされていた。
同日午後10時頃、看護師の観察によれば、本件褥瘡からの滲出液と出血がオムツまで汚染していた。仙骨部には黒色化した皮膚があり、その周囲の皮下がぶよぶよしている状態であった。肛門部には軟便が付着し、更に便がみえたため、看護師は、摘便し、本件褥瘡を洗浄した上、ガーゼを当てた。
午後10時30分時点のAの状態は、血圧が58/28、脈拍が86であったが、意識ははっきりしていた。看護師は、血圧低下の原因を、「摘便でかなり多量の排便による腹圧の低下と体位変換をしたためか」と看護記録に記載している。
しかし、午後10時45分頃から、Aは、血圧が46/20とさらに低下し、PVC(心室性期外収縮)を散発するようになった。
1月16日夜の当直医師は、血圧の低下を聞き、◇らに連絡するとともに、採血をし、オリベスKを輸液した。
1月17日午後1時頃、Aは、病室を移ったが、看護師が声をかけても返答せず、開眼もしない状態であった。
午後1時30分、本件褥瘡からは腐敗臭があり、看護師が観察すると、四角に圧迫痕があった。本件褥瘡部分は、一部を開放していたので、これを軽く圧迫すると、便臭がし、腐敗汁が多量に排出され、これを処置したガーゼは200gになった。
看護師は、この内容を看護師長に報告し、午前1時40分頃、本件褥瘡を洗浄した上、ガーゼで保護した。
H医師は、このころ、本件褥瘡を観察し、褥瘡感染から敗血症への進展を疑った。さらに、診療録には、午後2時57分付けで、「仙骨部中心に20cm程度の褥瘡あり。正中から右側に表皮が完全に黒色化。直径7cmくらい。圧迫にて血液様の暗赤色の排液あり。深部がやわらかく、スポット化している可能性がある」と記載した。
H医師は、切開術の適応について専門の医師と相談することとし、看護師に対しては、褥瘡の経過をデジタルカメラで撮影して記録するよう指示した。
同日午後3時38分頃、本件褥瘡から、約200gの腐敗臭を伴う血性の排液があった。
H医師は、循環血液量を確保するため、Aに対し、デキストラン250mlを補液した。
H医師は、1月18日午前8時38分頃、整形外科の医師に、Aに対する褥瘡除去の手術適応について相談した。その結果、本件褥瘡のデブリードマン(壊死組織を切除することで、他の組織への影響を防ぐ外科的処置)を行うこととなった。
同日午後7時15分頃、Aに対し、本件褥瘡のデブリードマンが実施され、壊死した皮膚を切除した箇所には、ヨードホルムガーゼを詰めて保護した。
同日午後9時頃、本件褥瘡から淡血性の滲出液が認められたため、看護師は、洗浄の上、ガーゼを交換した。
1月19日午後1時頃、本件褥瘡に対し、再度デブリードマンが実施された。創部はかなり汚く、腐敗臭もあるため、まだしばらくはデブリードマンが必要であると判断された。
同日午後5時30分頃、本件褥瘡から滲出液が認められたため、看護師は、洗浄の上、ガーゼを交換した。
1月20日午前5時頃、本件褥瘡から多量の滲出液が認められたため、看護師は、洗浄の上、ガーゼを交換した。
同日午後2時30分頃、本件褥瘡に対しデブリードマンが実施された。右腰部の2時から4時の方向に10cm以上のポケットがあり、膿が多量に排出された。左臀部の方向にもポケットがあった。
医師は、看護師に対し、日に日によくはなっているが、毎日処置が必要である旨話した。
Aは、同日午後7時の時点で、血圧168/64、脈拍が108、体温が38.6度であったが、声をかけても全く反応がなく、深くて困難な呼吸が見受けられた。
1月20日午後11時頃から、Aの脈拍が徐々に低下し始めた。
同月21日午前零時頃からは、血圧が低下し始めるとともに、下顎呼吸(瀕死時の患者にみられる、下顎だけを動かすあえぐような呼吸)をするなど、呼吸状態の悪化が認められた。
その後、Aは、午前3時12分、死亡した。死亡の直近に行われた血液検査の結果は、CPRが18.66、WBCが26400であった。
そこで、Aの相続人である◇ら(Aの妻及び子ら)は、Aは、△施設がAの褥瘡の適切な管理を怠ったため、褥瘡の悪化に起因する敗血症を発症し、死亡したと主張して、入居契約及び特定施設入所者生活介護利用契約の債務不履行並びに不法行為に基づき、△に対し、慰謝料等の損害賠償請求をした。
(損害賠償請求)
- 請求額:
- 入所者遺族4名合計6747万9282円
(内訳:入所者の慰謝料3000万円+年金の逸失利益262万6941円+遺族固有の慰謝料4名合計2500万円+葬儀費用385万2341円+弁護士費用600万円)
(裁判所の認容額)
- 認容額:
- 入所者遺族4名合計2160万1490円
(内訳:入所者の慰謝料1200万円+年金の逸失利益210万1493円+遺族固有の慰謝料4名合計400万円+葬儀費用150万円+弁護士費用200万円。遺族が複数につき端数不一致)
(裁判所の判断)
入所者の褥瘡の悪化に関して老人ホーム側に債務不履行・注意義務違反があるか否か
この点について、裁判所は、△施設は、介護付き老人ホームとして、入居契約及び特定施設入所者生活介護利用契約に基づき、Aに対し、介護、健康管理、治療への協力等のサービスを提供する義務を負っていたと指摘しました。
ところで、褥瘡は、身体の一部に持続的な圧迫が加わることにより、皮下の血流が阻害されて生じる皮膚褥瘡であるが、Aは、△施設への入居当時、87歳と高齢であり、一般に、高齢者は加齢による乾燥等の皮膚変化や、創傷治療能力の低下のため、褥瘡を生じやすいとされているとしました。しかも、Aは、一日のほとんどをベッドに寝た状態で過ごし、移動、食事、衣服の着脱、清拭等の日常生活全般に介助を要するというように、運動量が著しく低下しており、自発的な体位変換による除圧が困難な状態であったとしました。また、糖尿病にり患していたため、血管が閉塞しやすい傾向にあり、血流が阻害しやすい状態であったと指摘しました。このように、Aは、もともと褥瘡を生じやすく、また、褥瘡が治りにくい要因を有していたということができると判示しました。
裁判所は、そして、△施設は、Aの入居に当たっては、T医師からの診療情報提供及びK訪問看護ステーションからの看護情報提供を受け、Aの心身の状態並びに本件褥瘡の存在及びその悪化に注意を要するとの情報を把握していたと指摘しました。
裁判所は、そうすると、△施設は、上記のサービス提供義務の具体的内容として、Aにつき、2時間ごとの体位変換による除圧、患部の洗浄等による清潔の保持その他の適切な褥瘡管理を行い、本件褥瘡を悪化させないよう注意すべき義務を負っていたというべきであると判示しました。
しかるに、本件褥瘡は、平成18年1月8日頃以降、AがN病院へ救急搬送された同月16日までの間に、拡大、悪化し、細菌感染を起こしたと指摘しました。
裁判所は、本件褥瘡が感染し、敗血症を引き起こした原因菌は、腸管内に常在し、糞便から分離されて感染症の原因となることがある腸球菌であったと考えられるとしました。Aは、排便に関しておむつを使用していたが、△施設への入居中、1月11日と同月14日には、仙骨部等に便汚染が認められたことがあったとしました。なお、患部の便汚染は、便の成分によりスキンバリアが破壊されるため、炎症、びらん等を引き起こし、褥瘡自体の悪化にもつながりやすいものであると指摘しました。
裁判所は、また、本件褥瘡には、本件施設の看護師が最後にデュオアクティブを貼り替えた1月14日午前10時以降、デュオアクティブ1枚が、そのままの大きさ(10cm×10cm)で貼られていたと指摘しました。その前にデュオアクティブを貼り替えた同月11日の時点では、一枚の四分の一(5cm×5cm)程度を使用していたことからすると、本件褥瘡が、同日から同月14日にかけて、拡大、悪化したことが推認されると判示しました。
この点、デュオアクティブの医薬品添付文書には、使用上の注意として、「創に臨床的感染が認められた場合には、原則として使用を中止し、適切な治療を行うこと。」、「皮膚障害と思われる症状が現れた場合には、使用を中止し、適切な治療を行う。」と記載されている。しかしながら、△施設の看護師は、デュオアクティブの使用を続け、Aの本件褥瘡を医師に診せることをしなかった。
裁判所は、以上によれば、△施設の、Aに対する、褥瘡の清潔の保持には不十分な点があったといわざるを得ないと判示しました。
裁判所は、また、△施設は、Aを速やかに医師に受診させる等の義務も尽くさなかったと判示しました。
確かに、△施設では、本件褥瘡に関し、おおむね2時間ごとの体位交換を行い、ダラシン錠を服用させ、患部の洗浄、指示されたとおりの3、4日おきのデュオアクティブの交換等の処置を行っていた(T医師から褥瘡の治療薬として処方されていたケーベンクリームを患部に塗布していたことを認めるに足りる証拠はないとしました。)。しかしながら、本件褥瘡が、遅くとも1月11日頃以降、拡大、悪化し始めてからの対応として、このような処置等のみでは足りないというべきであると判示しました。
裁判所は、したがって、△には、Aに対する適切な褥瘡管理を行い、本件褥瘡を悪化させないよう注意すべき義務の債務不履行及び注意義務違反があったと認めることができると判断しました。
以上から、裁判所は、上記(裁判所の認容額)の範囲で◇らの請求を認めました。この判決は控訴されましたが、和解に至り、訴訟は終了しました。