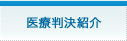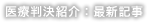大阪高等裁判所令和2年11月26日判決 医療判例解説(2021年12月号)95号65頁・ウェストロージャパン
(争点)
- 医師に術前の説明義務違反があったか否か
- 医師に術後の説明義務違反があったか否か
*以下、控訴人兼附帯被控訴人(1審原告)を◇1ないし◇4、被控訴人兼附帯控訴人(1審被告)を△と表記する。
(事案)
A(死亡当時51歳の男性・従業員13名程の建設業を営む会社の代表取締役)は、平成26年10月頃、W病院の脳ドックの頭部MRA検査により左椎骨動脈の脳動脈瘤を指摘され、同月14日、同病院の紹介により特別地方公共団体である△(企業団)の設置運営する病院(以下「△病院」という。)脳神経外科を受診した。△病院の脳神経外科部長であるB医師は、頭部MRI検査の結果、Aに左椎骨動脈瘤8~9mm(以下「本件脳動脈瘤」という。)を認め、4年前に比べて明らかに増大していたことから、Aに対して破裂の危険性が高まっているとして治療を勧めた。
Aは、同日、△との間で、本件脳動脈瘤の診療を目的とする診療契約を締結した。
B医師は、平成26年11月11日の診察時において、Aに対し、本件脳動脈瘤は、5年前に比べて明らかに増大傾向にあることから治療するのが望ましいこと、治療を行う場合、単体的なコイル塞栓術の適応になく、クリッピング術ないしバイパス術及びコイル塞栓術の併用のいずれかとなり、どちらも開頭手術を必要とすること、もっとも、本件脳動脈瘤は脳の深い位置にあり、合併症のリスクがあることから、現時点では画像診断を厳重に行いながら、形態変化があれば、手術を受けることを勧めた上で、仮に、現時点において手術を受ける場合、手術は90%うまくいくと考えているが、手術には神経圧迫等に伴う様々な合併症、場合によっては生命の危険を伴うリスクもあることを説明した上で、次回の診察日を2週間後として、それまでによく考えて決めるよう伝えた。
Aは、開頭手術を受けることには強い抵抗感があったものの、経過観察中に、本件脳動脈瘤が破裂することを懸念し、◇1(Aの妻)と検討した結果、本件脳動脈瘤が増大傾向にあり、破裂の危険があることを考えれば、手術が90%うまくいくのであれば、トラックを運転中に本件脳動脈瘤が破裂するよりも、元気なうちに手術を受けておいた方がよいと考え、くも膜下出血の予防を目的とする脳動脈瘤流入血管クリッピング術(以下「本件手術」という。)を受けることを決断した。
Aは、平成27年1月6日、本件手術のために△病院に入院し、翌7日、B医師を執刀医として左後頭下開頭による本件手術を受けた。本件手術の予定時間は10時間、使用予定のクリップ数は1本であったが、開頭範囲の拡大により、手術時間は13時間、使用クリップ数は2本となった。
Aは、本件手術後、飲み込みにくい、声が出しにくいなどの嚥下障害ないし発声障害等の症状が出現し、CRPの数値も日を追うごとに上昇し、体温も解熱剤を使用しない限り、37度台後半から38度を超える状態(同月12日まで)が続いていた。なお、本件手術により神経障害としての合併症が生じ得ることについては、Aと◇1も術前に説明を受けていた。
Aは、同年1月15日以降、傾眠が強く、発語の少ない状態が続き、瞳孔の不同状態やスローな対光反射が見られるようになり、歩行時のふらつきにより、転倒することもあったほか(15日、17日)、自ら胃管や点滴の針を抜去したり(15日)、◇1との会話において「カニは注文したんか。」などと趣旨不明の発言をしたり(16日)、リハビリテーションにおいても、終始、反応に乏しい覚醒度の低い状態であり、立位や歩行にふらつきが見られ、指示が伝わりにくく、終了を求めても延々と同じ動作を続けたりしたことなどから、担当医師は、Aの意識レベルに問題があると感じた(16日)ことがあったところ、◇1も、看護師に対し、Aが歩行中に転倒して頭部などを打ったことや、このような意識状態が不安定で不穏な行動が続いていることなどが心配である旨伝えていたにもかかわらず、B医師あるいは他の医師から特段の説明はなかった。
17日には、◇1は、回診に訪れたB医師に対し、Aの状態について、異常な行動が見られることや、目の焦点も合っていないことなどの不安を伝え、検査や手術の必要性について尋ねたものの、B医師は、栄養が不足していることによるものであり、検査や手術の必要はない旨述べるにとどまった。
Aは、同年1月19日、水頭症が原因とみられる意識障害を生じ、左右脳室のドレナージ術が行われた。この時採取した髄液を検査したところ、Aが髄膜炎を発症していることが判明した。
なお、B医師は、Aの容態が悪化して頭部MRI検査が緊急実施されるまでの間、経過観察を続ける一方で、Aのこれまでの症状等の原因や経過観察を続けることとした理由その他今後の見通し等について、◇1に具体的な説明をすることはなかった。
Aは、同年1月25日には自発呼吸ができなくなって脳死状態となり、同年5月7日、重症脳室炎及び重症髄膜炎により死亡した。
そこで、◇ら(◇1および子ら)は、△に対し、△病院の医師には、術前・術後の説明義務違反・術後管理義務違反等があるとして使用者責任又は診療契約の債務不履行に基づく損害賠償をした。
原審(令和元年9月20日神戸地方裁判所判決)は、術前の説明義務違反を認めたが、術後の説明義務違反および術後管理義務違反はいずれも認められず、上記説明義務違反と死亡との間に相当因果関係は認められないと判断し、説明義務違反(不法行為)に基づく慰謝料等として合計450万円の限度で◇らの請求を認容した。
これに対し、◇らが、これを不服として控訴を提起したところ、△も附帯控訴をした。
(損害賠償請求)
- 請求額:
- 遺族合計1億4532万0445円
(内訳:不明) - 原審認容額:
- 遺族合計450万円
(内訳:慰謝料400万円+弁護士費用50万円)
(控訴審裁判所の認容額)
- 認容額:
- 遺族合計660万円
(内訳:慰謝料600万円+弁護士費用60万円)
(裁判所の判断)
1.術前の説明義務違反について
この点について、控訴審裁判所は、Aは、B医師から、本件脳動脈瘤について、当面、経過観察とすることを勧められているところ、経過観察のメリットの1つに開頭手術に伴うリスクを避けることがあるのは明らかであることからすると、経過観察を選択することのメリットについて、一応の説明はなされているものと解されると判示しました。しかしながら、認定事実によれば、本件脳動脈瘤は、5年前と比較して明らかな増大傾向にあり、治療が望ましいと考えられるというのであり、また、一般的に未破裂脳動脈瘤をそのままにしておくことによって、自然経過的にそれが消失したり、手術の難易度が低下したりするものではないことを考えると、破裂の危険性が高くなっていることが窺われる本件脳動脈瘤について、これを保存的経過観察とする選択肢に、どのような理由(医学的根拠)に基づく合理性があるといえるのか判然とせず、その一方で、本件脳動脈瘤をそのままにすると、あるとき突然破裂する可能性もあるというのであれば、このような説明を受けたAとすれば、経過観察することのメリットよりも、これを放置することの不安が大きくなるのも無理はないところであり、しかも、手術の成功率は90%というのであるから、その裏返しにより、合併症のリスクが10%あることを推測したとしても、その時点において経過観察とすることのメリットを理解することは困難であったというべきであると判示しました。
また、B医師は、11月11日の診察時において、Aに説明をする際、本件脳動脈瘤については、手術を選択するのではなく、経過観察を選択するのがよいと考えていたというのであるから、そのように考える合理的理由があったと考えられ、その具体的理由については、同日の診療録に明示的な記載はないが、「厳重な画像F/Uを行い、再度、形態変化があれば手術をお勧めした。」との記載があることからすると、現状での危険は必ずしも高くないとの判断があったものと窺われるが、そもそも本件脳動脈瘤は増大傾向にあるのに、その増大、拡大の経過を見た上で手術を受けるという選択が、どのような合理的理由に基づくのかを、直ちに理解することは困難であったというべきであると指摘しました。
裁判所は、そうすると、Aは、11月11日の診察時における説明では、本件手術以外の選択肢である経過観察を選択することにより、開頭手術に伴うリスクを避けるメリットと、増大傾向にある本件脳動脈瘤の手術を先送りすることによるデメリットを比較するに当たり、経過観察を選択することにはどのような合理的理由があるのかを正しく理解することなく、本件手術を選択したものであって、このようなAの選択は、合理的な理解の下での自己決定とはいえないというべきであると判断しました。
裁判所は、B医師は、11月11日の診察時において、Aに対し、本件手術を受けるか否かの選択を求めるに当たり、本件脳動脈瘤の当時の状況及び関連する医学的知見に照らして、経過観察に関する必要かつ適切な情報を提供したとはいえず、それを選択し得るのにわかりやすい説明を怠ったとして、説明義務違反があったといわざるを得ないとしました。
2.術後の説明義務違反の有無について
この点について、裁判所は、B医師は、遅くとも◇1が、B医師に対して直接にAの現状について説明を求め、検査や手術等の必要性について尋ねた時点において、◇1が不安に思っているAの具体的症状について、考えられる原因や今後の見通し等(現時点において検査や手術等が必要でないのであれば、どのような事態になれば検査、手術等が必要となるのか、仮に、引き続き、経過観察とすることでよいと考えているのであれば、その理由など)を踏まえ、◇1の疑問点に答える形で、できるだけわかりやすく説明すべき義務があったと解するのが相当であるとしました。
しかしながら、B医師は、Aの術後の状態、症状等について、◇1から要望があったにもかかわらず、必要かつ適切な情報を提供することを怠り、◇1の不安や疑問等について答えようとする説明態度ではなかったと認められるのであって、主治医としての術後の説明義務違反に該当すると言わざるを得ないとしました。
以上から、裁判所は、上記(控訴審裁判所の認容額)の範囲で◇らの請求を認め、その後判決は確定しました。