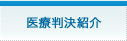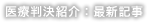東京高等裁判所平成30年9月26日判決 ウェストロー・ジャパン
(争点)
平成23年X線検査の終了後、Aの胃の穹窿部に隆起性病変があることを認識し、その内視鏡検査の必要性を認識していた医師につき、X線検査の診断内容をAに通知して医療機関において精密検査を受診するよう指導すべき注意義務違反の有無
*以下、控訴人(原審原告)を◇1ないし◇3、被控訴人(原審被告)を△1及び△2と表記する。
(事案)
A(死亡時78歳)は、医療社団法人である△1の開設するクリニック(以下「△診療所」という。)において、△1の代表者兼△診療所の医師である△2医師を担当医師として、平成12年以降毎年胃がん検診(C市が実施する胃がん検診事業(以下「本件検診事業」という。)に係る個別検診方式によるもの)を受診していた。
平成21年以降、△2医師は、△診療所において、Aに対し、平成21年X線検査(同年10月14日)、平成22年内視鏡検査(同年2月15日)、平成22年X線検査(同年12月1日)、平成23年X線検査(同年7月16日)を行っていた。
Aは、平成24年8月2日、肝臓がんにより死亡した。
そこで、Aの相続人である◇ら(妻及び子)は、△らに対し、△2医師には、上記胃がん検診に関して注意義務違反があり、これにより、Aの死亡又はその生存に係る相当程度の可能性の侵害に係る損害が発生したなどと主張して、△1に対して医療法68条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条又は債務不履行等による損害賠償請求権に基づき、また、△2医師に対しては不法行為による損害賠償請求権に基づき、連帯して、各金員の支払いを求めた。
原審(平成30年5月26日東京地裁判決)は、平成23年X線検査の診断内容をAに通知して医療機関において精密検査を受診するよう指導すべき注意義務を怠ったという△2医師の注意義務違反を認め、この注意義務違反とAの死亡との間に相当因果関係を認めることはできないが、△2医師がこの義務を尽くしていれば、Aがその死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性があったとして請求を一部認容した。
それを不服として◇らが控訴した。
(損害賠償請求)
- 請求額:
- 遺族3名合計6019万0099円
(内訳:慰謝料1000万円・その他の内訳は不明)
(原審及び控訴審裁判所の認容額)
- 認容額:
- 遺族3名合計220万円
(内訳:慰謝料200万円+弁護士費用20万円・その他の内訳は不明)
(裁判所の判断)
平成23年X線検査の終了後、Aの胃の穹窿部に隆起性病変があることを認識し、その内視鏡検査の必要性を認識していた医師につき、X線検査の診断内容をAに通知して医療機関において精密検査を受診するよう指導すべき注意義務違反の有無
この点について、遺族側は、△2医師は、平成23年X線検査(平成23年7月16日)の終了後、同月21日までにAの胃の穹窿部に隆起性病変があることを認識し、その内視鏡検査の必要性を認識していたのであるから、遅くともその1週間後である同月28日までに、上記X線検査の診断内容をAに通知して医療機関において精密検査を受診するよう指導すべき注意義務があったのに、これを怠った旨主張しました。そして、早期発見・早期治療という胃がん検診の目的及びC市と医師会との「健康増進事業契約書」並びに胃がん検診実施要領に照らせば、検診医は、読影委員会による2次読影の結果が判明する以前であっても、異常所見を認識した時点か、どれほど遅くとも同時点から1週間以内にその旨を速やかに受診者に通知し、精密検査を受診するよう指導すべき注意義務を負っていたと主張しました。
しかし、控訴審裁判所は、原判決と同様、△2医師の注意義務違反は、読影委員会による2次読影の検査が判明した平成23年8月4日以降において認められるというべきであると判断しました。そして、◇らの指摘する証拠を踏まえて本件検診事業に係る個別受診方式による検査結果の通知等に関する仕組みについて検討しても、同仕組みにおいては、個別受診方式で胃部X線検査を実施した医師が、当該X線写真の1次、2次読影結果に基づいて精密検査を要するとの所見を得たとき、当該受診者に対し、速やかにその旨を通知すべきものとされている旨認定するのが相当であると判示しました。そうすると、2次読影結果が判明する前に、法的義務として △2医師において、本件注意義務が発生していたと帰結することを意味する◇らの見解は相当とはいえないとしてこの点に関する◇らの主張を採用しませんでした。
以上から、控訴裁判所は、上記(原審及び控訴審裁判所の認容額)の範囲で◇らの請求を認めました。