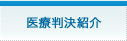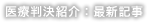東京地方裁判所令和6年9月13日判決 判例タイムズ1531号170頁
(争点)
医師の注意義務違反と死亡との間の因果関係及び生存の相当程度の可能性の有無
*以下、原告を◇、被告を△1及び△2と表記する。
(事案)
W(昭和25年生まれの男性)は、平成28年10月12日、医療法人である△1の開設する病院(以下「△病院」という。)に蜂窩織炎で入院し、同年11月8日に腹部造影CT検査を受けた。
△病院に勤務する△2医師は、この腹部造影CT検査の読影報告書を受け取った。同読影報告書には、「肝硬変、肝S7多血性病変、肝S2に早期増強域:S7病変はHCCに相当。S2についてはAPシャントとの鑑別が問題となる。EOB造影MRIの適用です。」と記載されていた(なお、HCCとは肝細胞癌のことを指す。)が、△2医師は、Wに対し、EOB造影MRI検査を実施しなかった。しかしながら、Wは、平成28年11月8日当時、肝S2に腫瘍径13mm、ステージⅠ、腫瘍数1の肝細胞癌を発症していたことが、後に判明した。Wは、令和元年7月2日、腹部造影CT検査を受け、その際、肝S2に腫瘍径56mm、ステージⅡの肝細胞癌が発見された。
Wは、P大学医学部附属Q医院(以下「Q医院」という。)消化器内科のR医師(以下「R医師」という。)による焼灼療法を希望し、同月27日に△病院に入院した。この際、Q医院の医師は、Wに対し、肝切除が第一選択となること、焼灼療法は標準治療となっていないこと、どうしても希望するのであれば焼灼療法をすることを説明した。Wは、焼灼療法を希望し、R医師によるマイクロ波焼灼術及びラジオ波焼灼術を受け、同年8月18日にQ医院を退院した。
Wは、その後も、Q医院に通院し、検査を受けていたところ、令和2年1月27日のEOB造影MRI検査により、肝S2に8mmの結節病変が発見された。そして、同年4月1日のEOB造影MRI検査を得て、肝細胞癌の再発と診断された。その後、再びラジオ波焼灼術等を受けたものの、本件訴訟提起後の令和5年9月27日、肝細胞癌破裂により死亡した。
そこで、Wは、△2医師が造影CT検査の結果を受け、平成28年11月8日以降速やかにEOB造影MRI検査等の検査をする義務があったにもかかわらず、それを怠ったと主張して、△らに対し、不法行為(使用者責任)による損害賠償請求を提起し、W死亡後は◇(Wの姉でありWの損害賠償請求権を単独で相続した)が訴訟を承継した。
なお、本件では、△2医師には、腹部造影CT検査の結果を受け、平成28年11月8日以降速やかにEOB造影MRI検査等の検査をする義務があったにもかかわらず、それを怠った注意義務違反(以下「本件注意義務違反」という。)が存在することについては、◇と△らとの間に争いがない。
(損害賠償請求)
- 患者(遺族)の請求額:
- (ア)2401万8281円又は(イ)1136万8281円
-
- (内訳:
- (ア)因果関係(本件注意義務違反がなければWが死亡時点でなお生存していた高度の蓋然性)が認められる場合
死亡慰謝料2000万円+葬儀関係費用150万円+診療記録開示手数料5万0506円+医療保険料28万4295円+弁護士費用218万3480円) - (イ)本件注意義務違反がなければWが死亡時点でなお生存していた相当程度の可能性のみ認められる場合
慰謝料1000万円+診療記録開示手数料5万0506円+医療保険料28万4295円+弁護士費用103万3480円)
(裁判所の認容額)
- 認容額:
- 918万4801円
(内訳:慰謝料800万円+診療記録開示手数料5万0506円+医療保険料28万4295円*+弁護士費用85万円) - *平成28年11月から令和元年7月までの33か月の間にWが払った「重大疾病保障定期保険」(癌などの所定の重大疾病にかかり所定の状態となったときに保険金が支払われる)の保険料合計額。平成28年11月8日時点でWが肝細胞癌であるとの確定診断を受けていれば、その時点で保険金を請求することとなり、保険料の支払いをすることはなかったものと推認される。
(裁判所の判断)
医師の注意義務違反と死亡との間の因果関係及び生存の相当程度の可能性の有無
この点について、裁判所は、肝細胞癌は、治療方針が肝切除であっても、焼灼療法であっても、5年再発率が70から80%とされ、再発率は高いと指摘しました。また、ステージⅠの肝細胞癌であっても、5年相対生存率が63%から70%、10年相対生存率が34.5%とされ、R医師によるラジオ波焼灼術を受けた肝細胞癌患者では、単発、腫瘍径3cm以内、Child―Pugh分類Aに限った場合でも、5年生存率は74%、10年生存率は41.3%であるため、生存率が高い疾患であるとはいえないと判示しました。
裁判所は、これらの事実関係を踏まえると、Wが、平成28年11月8日以降速やかにEOB造影MRI等の検査を受けることにより、ステージⅠの肝細胞癌であるとの確定診断を受け、その治療を受けていたとしても、令和5年9月27日までの約7年間のうちに肝細胞癌が再発する可能性は相当程度に高いものであったといわざるを得ず、その結果死亡していた可能性があることは否定できないと判示しました。
そうすると、本件注意義務違反がなかったとした場合に、Wがその死亡の時点においてなお生存していたであろうことを是認し得る高度の蓋然性があるものと認めることはできないと判断して、本件注意義務違反とWの死亡との因果関係を否定しました。
裁判所は、もっとも、肝細胞癌の肝切除の場合の予後因子として、肝瘍径、腫瘍数、脈管侵襲の存在、肝機能が挙げられているところ、Wは、平成28年11月8日時点で、肝細胞癌の腫瘍径は13mmと比較的小さく、腫瘍数は1個のみ、脈管侵襲はなく、Child―Pugh分類Aと肝機能が良好であったのであるから、比較的良好な予後が期待できる状態であったということができると指摘しました。このことに、肝細胞癌患者の相対生存率も考慮すれば、仮にWが、同日以降速やかにEOB造影MRI等の検査を受けることにより、ステージⅠの肝細胞癌であるとの確定診断を受け、その治療を受けていれば、その死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性が存在するものと認められると判示しました。
以上から、裁判所は、上記(裁判所の認容額)の範囲で◇の請求を認め、その後判決は確定しました。