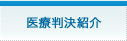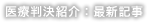今回は、癌で死亡した患者につき、いわゆる「相当程度の可能性の侵害」が認められた裁判例を2件ご紹介します。
最高裁判所平成12年9月22日判決は、「医師の医療行為が、その過失により、当時の医療水準にかなったものでなかった場合において、右医療行為と患者の死亡との間の因果関係の存在は証明されないけれども、医療水準にかなった医療が行われていたならば患者がその死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性の存在が証明されるときは、医師は、患者に対し、不法行為による損害を賠償する責任を負うものと解するのが相当である。」と判示しています。
死亡との因果関係が認められるためには、「医師が注意義務を尽くしていれば患者がその死亡の時点でなお生存していた高度の蓋然性」が証明される必要がありますが、そこまでの証明ができなくても、「相当程度の可能性」の存在が肯定されれば、その「相当程度の可能性」が侵害されたことに対する慰謝料が認められることとなります。
ただし、賠償額は主に慰謝料となるため、死亡との因果関係が認められた場合と比較して、低い金額にとどまります。
No.532の事案では、遺族側は、医師の過失と患者の死亡との間の因果関係の存在も主張しました。しかし、裁判所は、本件胃がんに係る手術が1カ月程度早く実施されたとしても、既にその時点において本件胃がんの血行性転移が生じていた可能性は相当にあったものと考えるのが合理的であり、患者が実際の死亡日に死亡することを避けられた高度の蓋然性があったとまでは認められないと判示して、遺族側の上記主張を採用しませんでした。
No.533の事案では、裁判所は、腹部造影CT検査の読影報告書には、幹細胞癌の疑いやEOB造影MRI検査の適応の記載が含まれており、早期幹細胞癌の検出においては同検査が最も有用であったと判示し、腫瘍径が小さいほど予後が良いこと、肝細胞癌の再発率は高いこと等を考慮すると、幹細胞癌の確定診断を速やかに行い、早期に治療を開始するために、被告医師はEOB造影MRI検査を速やかに行うべきであったにもかかわらず、被告医師は約2年8か月もの長期間にわたり同検査等をすることなく、幹細胞癌を発見することができなかった(その結果治療開始が3年近くも遅れ、肝細胞癌が進行し、腫瘍径は13mmから56mmへと4倍以上に巨大化)のであって、被告医師の注意義務違反の程度は大きいとし、更に、患者は消化器専門医の受診を継続していたにもかかわらず、約2年8か月もの間、再発率が高く生存率の高くない疾患である幹細胞癌の確定診断を受けることができず、放置されたまま、その治療を受ける機会を失ったのであり、患者が、早期に発見されていれば完治できたのではないかとの期待を抱くのは無理からぬことであるところ、この期待を失わせる結果となった上に、交渉過程において被告病院の院長が注意義務違反を否定する発言をするなどしていたのであるから、患者の受けた精神的苦痛は極めて大きいというべきである旨判示して、慰謝料800万円が相当と判断しました。
両事案とも実務の参考になるかと存じます。