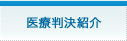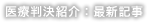青森地方裁判所平成21年12月25日判決 判例時報2074号113頁
(争点)
- 責任分担法理の準用による賠償額の減額の可否
- 逸失利益の算定
*以下、原告を◇1及び◇2、被告を△1及び△2と表記する。
(事案)
A(死亡当時16歳・重度の知的障害を有する男性)は自閉症、てんかん、行動障害及び重度の知的障害とされていたところ、平成15年1月29日に実施された知能検査ではIQ24と判定された。
△1は、第一種社会福祉事業として、知的障害児施設である△学園の設置経営や第二種社会福祉事業として、△学園等における障害福祉サービス事業を行うことなどを目的とする社会福祉法人であり、△2は平成16年7月21日、△学園の職員であった。
Aは、平成15年4月8日、児童福祉法に基づく措置決定により、△1の関連法人である学校法人Oが開設するO養護学校の高等部に入学し、△学園内にあるK寮に入所した。
平成16年当時の△学園においては、Uが園長を務め、副園長が1名、課長1名、課長補佐2名という体制のもとに、生活部と施設部が設置されていた。
同年度当時のK寮においては、中学生から作業班の利用者までの男性11名が入寮し、「自分のことは自分で行う、出来るようになる」をモットーとし、個々の入所者について、適切な目標設定を図り、生活習慣や社会性の育成確立を目指すものとされていた。また、入所者の日課としては、午前6時に起床し、午前7時から朝食と後片付け、掃除等を行い、高等部の生徒は午前8時30分に登校して、午後4時に下校し、午後5時から入浴と洗濯を行い、午後6時に夕食と洗面を経て、午後9時に就寝することとなっていた。
本件死亡事故の発生当時、K寮における担当職員は4名であり、これらの担当職員は入所者が行う日課の支援や介助等を行っていた。
なお、夜間における利用者の支援や介助等については、△1の当直職員が行っていた。
△学園においては、本件死亡事故後の平成19年当時には施設利用者の「入浴支援マニュアルリスクレベル表」が作成されており、この中で、障害状況としててんかん発作を有する者が入浴する場合は、リスクレベルが高いものとされ、遵守事項として、常に職員が浴室内にいることとされているが、本件死亡事故が発生した平成16年当時は、△1職員の間で入浴中に利用者がてんかん発作を起こした場合に、死亡事故につながる危険性があると認識されていたものの、上記のようなマニュアルは作成されておらず、利用者が入浴する際は、5分ないし10分に1回の頻度で見守りをする運用とされていた。
△1職員は、Aがてんかん発作を起こすことがあることを認識していたことから、基本的には、Aをてんかん発作を起こすことのある別の男性入所者と一緒に入浴させることとしていた。
Aは、平成15年11月26日、K寮の浴室で入浴中にてんかん発作を起こしたが、△1職員がこれに対応したため、命に別状はなかった。
平成16年7月21日午後3時ころ、△2は、△1の男性職員に対し、同日午後3時10分ころからAをK寮の浴室において入浴させるように指示し、同職員は、これに従い、同日午後3時25分ころからAを一人で入浴させた。そして、△2が同日午後3時35分ころに、同職員が同日午後3時42分ころに、それぞれ浴室に赴き、いずれの際にもAが入浴中であることを確認したが、△2及び同職員は、脱衣所に待機するなどして入浴中のAを常時見守ることはしておらず、また、△2は、その担当職務を引き継ぐべき他の職員に対し、Aが入浴中であることを告げることなく退勤した。
その後の同日午後3時50分ころ、△1の別の職員が浴室内を確認したところ、Aが浴槽内に沈んでいたため、同職員は直ちにAを浴槽から引き上げた上、心肺停止状態であったAに人工呼吸と心臓マッサージを施したが、Aは、同日午後5時5分、搬送先の病院で死亡が確認された(以下、「本件死亡事故」という。)。
そこで、◇ら(Aの両親)は、Aが寮の浴室内において溺死した事故について、担当職員であった△2及びその使用者である△1に対する安全配慮義務違反があったとして、債務不履行又は不法行為による損害賠償請求権に基づき、支払いを求めた。なお、◇らはAが同じ寮に入所していた成人男性から繰り返し受けた暴行被害についても△1に対して慰謝料を請求した。
(損害賠償請求)
- 請求額:
- (遺族両名合計)7339万7664円
(内訳:暴行被害に対する慰謝料100万円+暴行被害の報告義務違反に対する両親固有の損害100万円+死亡慰謝料2000万円+逸失利益4075万6274円+両親固有の慰謝料2名合計600万円+葬儀費用150万円+うつ病になった母親の通院治療費14万1390円+弁護士費用300万円。なお暴行被害についての請求の被告は△1のみ)
(裁判所の認容額)
- 認容額:
- (遺族両名合計)3247万0098円
(内訳:暴行被害に対する慰謝料14万円+死亡慰謝料1800万円+逸失利益603万0098円+葬儀費用150万円+両親固有の慰謝料2名合計400万円+弁護士費用280万円。なお、暴行被害についての請求が認容された被告は△1のみ)
(裁判所の判断)
責任分担法理の準用による賠償額の減額の可否
裁判所は、まず、本件死亡事故に関し、△2がてんかん発作の危険性があるAの入浴時の見守りを怠り、かつ、他の職員に対する適切な引き継ぎを怠ったことについては△らも認めており、争いがないと判示して、本件死亡事故につき△2が不法行為に基づく損害賠償義務を、△1が使用者責任に基づく損害賠償義務をそれぞれ負うものと判断しました。
△らは、本件死亡事故は職員のケアレスミスによって発生したものであるとし、自閉症患者を含む障害者の施設環境が劣悪であって極めて厳しいものであるという現状等に照らし、信義則上の衡平原則に基づく責任分担法理を準用して慰謝料額等を減額すべきであると主張しました。
しかし、裁判所は、自閉症患者を含む障害者に対する福祉行政等の現状が不十分であるとしても、それを根拠として障害者施設における利用者に対する安全配慮義務の内容や程度が変わるものではなく、施設内において利用者の死亡事故を発生させることが許容されないことはいうまでもないところであって、また、本件死亡事故は、その内容や経緯に鑑みれば、△2のケアレスミスによって発生したものということもできないと判示して、△らの主張を採用しませんでした。
逸失利益の算定
裁判所は、前提として、Aは、重度の知的障害を有しており、K寮等の知的障害者支援施設において、就労も視野に入れた基本的な生活知識や技術等を教育されていたものであり、本件死亡事故当時には、身体的機能については何ら問題はなく、絵や写真等により行うべき作業を示されると、その内容を理解することができ、ドリルによる穴開けや釘打ちなど、危険性を伴うものの、操作自体は容易である工作機械や工具を用いた簡易な作業を行うことができたほか、平仮名や片仮名については読むことができたと判示しました。他方において、Aは、就労において必要不可欠というべき社会的規範やルール等において、なお不十分であったといわざるを得ず、Aの状況に鑑みれば、直ちに一般的な就労可能性があったとするのは困難というほかないと判示しました。
その上で、裁判所は、知的障害者が一般企業へ就労する機会が増えつつある現状に鑑みれば、健常者の賃金水準には劣るとしても、知的障害者がその有する能力を十分に活用することができる職場において、就労する機会を得て、授産施設における作業による賃金と比較すれば、高水準の賃金を得ることも可能な状況になりつつあるということができ、このような状況は、障害者に対する理解が遅々としたものではあっても、徐々に深化してきていることを示すものというべきであって、今後も将来にわたって、知的障害者がその能力を十分に活用することができる職場が徐々に増加することを期待し得るというものであると判示しました。
そして、死亡当時16歳にすぎなかったAも、今後の長い社会生活の中で、徐々にではあっても、その就労能力を高めることができた蓋然性があるのであるから、上記のような知的障害者雇用に関する社会条件の変化をも併せて考慮すれば、約50年にもわたる就労可能期間を残して死亡したAが、自閉症を含む重度の知的障害を抱えながらも、その就労可能な全期間を通して相当の賃金を得ることができた蓋然性を否定することはできないというべきであるとしました。
このように、Aは、その就労可能な全期間を通して、一定の生活支援及び就労支援を受けることを前提として、少なくとも最低賃金額に相当する額の収入を得ることができたと推認するのが相当であるというべきであると判示し、したがって、Aについては、最低賃金額を基礎収入として逸失利益を算定すべきであると判断しました。
以上から、裁判所は、上記(裁判所の認容額)の範囲で◇らの請求を認め、その後判決は確定しました。