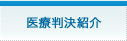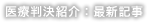東京高等裁判所平成11年9月16日判決 判例タイムズ1038号238頁
(争点)
- 死因とベッドからの転落との間に因果関係があったか否か
- 病院にベッドの転落防止措置を怠った過失があったか否か
*以下、原告を◇1及び◇2、被告を△と表記する。
(事案)
A(明治41年生まれ)は、膠原病の一種である結節性動脈周囲炎(PN)という難病に罹患していた。
Aは、市である△の運営する病院(以下「△病院」という。)に長期入院中であった。
Aの身体状態は、両足ともに膝の10センチメートル位上で切断されていて、ほとんどベッドの上で生活しており、手も指先が膠縮、変形して箸が持てない状態であり、日常生活においても、食事、起座、排泄、清拭等の全般にわたり看護師の援助が必要であった。A自身は残された機能をなるべく使うよう努力しており、例えば、洗面の際には、看護師が洗面器にお湯を入れてサイドテーブルの上に乗せると、Aが自分でタオルを絞って拭くとか、看護師が絞ってタオルを渡し、Aが自分で拭くとかというような状態であった。Aは、自分ではベッドの柵の上げ下げはできず、看護師がやっていた。 Aは、昭和54年10月に入り全身の状態が悪化し、中心静脈栄養による栄養を補給したり、ペインクリニックの点でも硬膜外神経ブロックもやれない(これをやると血圧が下がるため)ようになっていた。
昭和54年10月29日午前6時5分ごろ、Aは、看護師に起こされ、洗面の準備をした看護師が他の病室に行った後、ベッド上で自分で少し体を動かしているうちにこらえきれなくなって、ベッドの(仰向けに寝た患者から見て)左側に転落して、ビニール張りの床(床からベッド上まで約63センチメートル)に頭部(右額部)を打った。
Aがベッドから転落した時点でベッド柵は両側とも立てられていなかった。
△病院の看護師において Aの状況を観察し、特に意識状態に異変を感じなかったこと、その後、K医師や約2時間後には、主治医のU医師がAを診察し、意識状態、眼の状態(瞳孔の動き)、腱反射等の検査を行った上で、この時点でAに頭蓋内の出血はないと判断した。
Aは、翌日に急性副腎不全による高カリウム血症により死亡した。
そこで、Aの相続人である◇ら(子3名のうちの2名)は、△に対して、ベッドからの転落、その後の措置に△病院の医師、看護師らに過失があったなどとして、診療契約の債務不履行による損害賠償請求をした。
原審(長野地方裁判所諏訪支部平成10年3月17日判決)は、転落防止のためにベッドの柵を立てていなかった過失を認め、ベッドからの転落と死亡との間に相当因果があるとして、◇らの請求の一部を認容した。
これを不服として、◇ら及び△の双方が控訴した。
(損害賠償請求)
- 原審での患者遺族の請求額:
- 2名合計4060万円
(内訳:死者本人慰謝料の相続分2000万円+葬儀費用60万円+遺族固有の慰謝料2000万円)
- 控訴審での患者遺族の請求額:
- 2000万円
(内訳不明)
- 原審裁判所の認容額:
- 260万円
(内訳:死者本人慰謝料100万円+葬儀費用60万円+遺族固有の慰謝料100万円)
- 控訴審裁判所の認容額:
- 250万円
(内訳:死者本人慰謝料200万円+葬儀費用50万円)
(控訴審裁判所の判断)
1 死因とベッドからの転落との間に因果関係があったか否か
この点について裁判所は、まず、医師がAをベッドから転落して頭部を打ったものとして診察をし、それも複数の医師が別々に診察していることからみて、その時点でAの頭蓋内出血を疑わせるような状況はなかったものと認められるとしました。
そして、鑑定人がAの死因の最大関与因子としては高カリウム血症が考えられること、高カリウム血症と頭蓋内出血との関連性が乏しいことから頭蓋内出血が死因であることに消極的な結論となっていることや、消化管出血の可能性も検討し、死亡当日の血液検査所見が以前と変動が大きくないことから、急激な大量の消化管出血が出現していた可能性は極めて少ないとしていること、その上で、Aが長期にわたるステロイド投与を受けており、ベッドからの転落時に強い精神的なストレスを受けていること、直前までは腎機能は比較的良好に保たれていたのに急激に高カリウム血症になったこと等を総合して、急性副腎不全に陥った可能性が最も高いとの結論に至っていることを指摘しました。
その上で、裁判所は、Aがベッドから転落したことにより、これが原因となって、急性副腎不全をきたし、高カリウム血症により死亡したと認めるのが相当であると判示して、Aがベッドから転落したことと、Aの高カリウム血症による死亡との間には相当因果関係があると判断しました。
2 病院にベッドの転落防止措置を怠った過失があったか否か
この点について裁判所は、Aの身体状況等を考慮すると、Aは自己の体を支えること自体相当困難であり、特に、体勢が崩れるとこれを自己の力で立て直すのは極めて困難であることが容易に知れるところであって、これにAがほとんどベッドの上で生活しなければならない状態であったことを考え併せると、ベッドからの転落防止は当然看護する側で配慮しなければならない事柄であったと認定しました。
そして、Aのような身体状態の患者を入院させている病院としては、看護師等により患者に対し、具体的な看護をすることができる状態にない場合には、患者のベッドからの転落を防止するために、ベッドの柵を立てる措置をすべきであったということができるところ、Aの転落当時、具体的な看護をしている者はいなかった状態であるにもかかわらず、ベッドの柵が立てられていなかったのであるから、△にこの点において過失があったと判断しました。
以上から、控訴審裁判所は、上記(控訴裁判所の認容額)の範囲で◇らの請求を認めました。