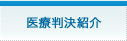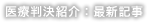横浜地方裁判所令和6年1月31日判決 判例タイムズ1531号177頁
(争点)
施設職員に過失があったか否か
*以下、原告を◇、被告を△と表記する。
(事案)
社会福祉法人である△が運営する障害者総合福祉施設(以下「△施設」という。)は、常時介護を要する重度障害者に対し、利用者個々の特性に応じた介護、訓練、医療等の必要な支援を行う施設であり、平成30年当時、その管理運営規程上、施設長及びサービス管理責任者各1名、非常勤医師2名、専従看護職4名、その他スタッフ40名余りが配置されていた。
A(死亡時28歳・男性)は、平成18年(高校生時)に交通事故に遭い、肢体不自由、四肢体幹機能障害、高次脳機能障害となり、平成19年4月26日に身体障害者手帳1級を交付された。
Aは、交通事故後、G病院に1年、リハビリテーション病院に6ヶ月入院し、平成23年4月頃以降、ケアセンターの生活介護を利用しながら父とともに生活していた。
Aは、平成26年11月21日、症候性てんかん発作(以下、この時の発作を「第1回発作」という。)を起こし、それ以降、抗てんかん薬カルバマゼピンを服用していた。
Aは、同年末に父が死亡し、ケアセンターの短期入所や生活介護を利用して生活していたが、食事、排泄、入浴等日常生活のほとんどの面で介助を必要とする状態にあり、◇(Aの母)が申し込んで平成27年10月1日に△施設に入所した。同月7日の入所面談において、Aが症候性てんかんを発症したこと、それ以降抗てんかん薬カルマゼピンを服用していることが△施設に伝えられ、入所中も△施設医師から同薬が処方されることになり、△施設が作成したAに関する利用者台帳、医師記録及び看護記録にもその旨が記載された。
Aは、第1回発作後、てんかん発作なく過ごしていたが、平成28年6月28日午後6時23分頃、△施設食堂エレベーター前においてけいれん発作(以下、この時の発作を「第2回発作」という。)を起こした。△施設職員が午後6時32分頃に救急要請し、救急隊の指示を受けて、Aをベッドに移しその気道確保に努めた。救急隊が午後6時38分頃に到着し、Aは午後6時52分にI病院に搬送され、てんかん重積(発作がある程度の長さ以上持続し又は短い発作でも反復してその間の意識の回復がないもの。てんかん重積の持続は死亡率を高め、神経学的後遺障害を残す要因となる。)と診断された。午後7時10分頃、同病院処置室にて発作が治まり、数分後に再発したものの、その後容体は安定し、Aは、翌29日には普段と変わらない様子で退院し、△施設に戻った。
この件を受けて、I病院の脳外科医師から、△施設職員(主任)及び◇に対し、今回のてんかん発作は、交通事故外傷によるもの、精神的なもの、疲れによるものなどが考えられること、CT検査等の結果は問題なく、イーケプラを追加処方して経過を見ること、生活は今までと同じで良いが、同様の症状が現れた場合は今回のように救急要請し救急隊到着までは気道確保及び状態観察に努めることとの説明があった。同職員(主任)から、△施設に対して救急搬送の経緯及び医師の説明が文書によって報告された。また、△施設作成のAの看護記録には、同じような発作が再度あったら、I病院を受診する旨が記載された。△施設医師は、同年7月頃、Aに対し、抗てんかん薬としてカルバマゼピンに加えて、イーケプラを処方し、Aは、その頃以降これらの薬を服用した。
Aは、その後てんかんの発作なく過ごしていたが、平成30年12月15日△施設において、症候性てんかん発作(以下、この時の発作を「本件発作」という。)を発症した。
Aは、△施設食堂において、夕食時に本件発作を起こし、自ら手を挙げてけいれんを訴えた。△施設職員は、午後6時48分にAが全身けいれん発作を起こし、声掛けに応じないことを確認し、午後6時55分にAをその居室のベッドに移した。
△施設職員は、午後6時58分にAの眼球が左右に転じ、鼻呼吸が荒く、泡を吐いていることを確認し、午後7時に居室の温度を上げてAの体を温めた。同職員は、午後7時02分にAのけいれんが継続していることを確認し、他の職員に報告するとともに上司の指示を仰いだが、午後7時28分に△施設サービスの全体を鑑みて様子を見るようにという指示を受けたため、Aの居室、ドアを開放したまま適時訪室する形をとることにした。
△施設職員は、午後8時にAのけいれんがなお治まらず、多量の唾液を出し、意識混濁が続いているのを確認し、改善の目処が立たないとして再び上司に連絡した。午後8時15分に救急要請の指示が下り、同職員は、午後8時26分に救急要請した。
救急隊が午後8時33分に△施設に到着したが、Aは、意識障害(痛み刺激に全く反応しない状態であるJCS300)があり、けいれんが顔面及び四肢に持続し、チアノーゼを呈して呼吸は浅く早い状態(SpO2値56%)であった。救急隊により、用手的気道確保処置及び10Lの酸素投与が行われたが、Aは、午後8時39分に眼球が上転し心肺停止となり、救急隊による胸骨圧迫及び換気による心肺蘇生処置が開始された。
Aは午後8時40分にI病院へ搬送され、午後8時42分に病院に到着し、午後8時43分に救急隊から同病院医師へ引き継がれた。同病院医師の治療により、午後8時54分に自己心拍が再開したが、その後3回ほどPEA(無脈性電気活動)となり、意識状態が改善することはなく、翌16日午前6時29分に死亡した。
そこで、◇が、△に対し、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償を請求した。
(損害賠償請求)
- 請求額:
- 4255万9718円
(内訳:葬儀費用150万円+逸失利益919万0653円+死亡慰謝料2800万円+弁護士費用386万9065円)
(裁判所の認容額)
- 認容額:
- 3587万2491円
(内訳:葬儀費用128万7230円+逸失利益732万4126円+死亡慰謝料2400万円+弁護士費用326万1135円)
(裁判所の判断)
施設職員に過失があったか否か
この点について、裁判所は、まず、△施設には、平成30年当時、重度障害者に対する医療等の必要な支援を行うため、医師、看護職、その他スタッフ等相当数の職員が配置されていたと認められるとしました。そして、△施設の管理運営規程上、職員は、利用者の病状の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに嘱託医に連絡する等の措置を講じ、嘱託医への連絡等が困難な場合は医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ずるものとされたこと、また、△施設にはけいれん発作の持続に対して有効な治療ができるような医療体制が構築されていなかったことが認められるとしました。
また、(1)Aの入所に際し、第1回発作及びそれ以降の抗てんかん薬の服用の事実が△施設に伝えられたこと、(2)△施設医師からAに同薬が処方されるとともに、利用者台帳等を通じて△施設内で Aのてんかん及び抗てんかん薬の服用に関する情報が共有されたこと、(3)第2回発作を受けて、Aに対する抗てんかん薬の処方が強化され、救急搬送の経緯及び同様の症状が現れた場合は、今回のように救急要請し救急隊到着までは気道確保及び状態観察に努めることというI病院医師の説明が、△施設職員(主任)から△に対して報告され、Aの看護記録にもそのような対応方針が記載されたことが認められるとしました。
医師の上記説明は、てんかんのけいれん発作が5分以上持続する場合は、てんかん重積となる可能性が高く、直ちに気道確保、酸素投与、ジアゼパム投与による治療を開始することが求められるという医学的知見を前提に、上記のような体制を持つ障害者福祉施設において、必ずしも上述のような医学的知見を持たずとも、Aに関する情報を共有している職員であれば、具体的にとることが可能であり、またとるべき対応を述べたものと考えられると指摘しました。そして、第2回発作時の救急要請が発作発生から約9分で実施されていることからすれば、それと相違ない時間内での速やかな救急要請を求めたものと理解できると判示しました。
裁判所は、上記事実を考慮すれば、△施設職員は、てんかんを持つAにけいれん発作が持続していることを認識した場合は、10分以内に救急搬送をすべき注意義務を負っていたと判断しました。
そして、△施設職員は、午後6時48分にAが全身けいれん発作を起こし、声掛けに応じないことを確認し、それから10分経過した午後6時58分にAの眼球が左右に転じ、鼻呼吸が荒く、泡を吐いていることを確認したのであるから、その時点で救急要請をすべき注意義務を負っていたといえると判示しました。しかし、△施設職員は、午後8時26分になって初めて救急要請したから、上記注意義務に違反したと認定しました。
なお、Aを担当した△施設職員は、午後7時02分に他の職員に報告し、上司の指示を仰いだところ、その上司から様子を見るようにという指示を受けたという事実が認められるが、Aの様子からは事態の緊急性は明らかであって、上司の指示は不適切というほかないから、この事実の存在によって注意義務違反に関する認定は左右されないと判示しました。
裁判所は、以上によれば、△施設職員は、遅くとも午後6時58分に救急要請すべき注意義務を負っていたのに、同注意義務に違反した過失があったと認められるとしました。
以上から、裁判所は、上記(裁判所の認容額)の範囲で◇の請求を認め、その後判決は確定しました。