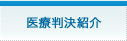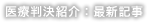東京高等裁判所平成11年9月16日判決 判例時報1710号105頁
(争点)
医師の説明義務違反があるか否か
*以下、控訴人らを◇1ないし◇4、被控訴人を△と表記する。
(事案)
A(死亡時72歳の女性)は、平成4年6月15日、国である△の経営する大学附属病院(以下「△病院」という。)で初診を受け、子宮癌と診断された。Aは平成4年7月7日△病院に入院し、主治医N医師が同月21日に手術(術式は準広汎子宮全摘術、両側附属器切除術、骨盤リンパ節郭清術)を施行した。その後の検査で、N医師は、Aの腫瘍は明細胞癌であると診断した。手術後、△病院は、Aに対し、抗がん剤アクチノマイシンD及びシスプラチンを使用する化学療法を施した。
平成4年当時の明細胞癌に対する化学治療は、標準的な方法が確立されていなかったが、△病院の研究グループに属するI教授は、平成3年に卵巣明細胞癌に対してアクチノマイシンDが感受性を有すると指摘する論文を公表しており、平成4年ごろには卵巣明細胞癌に対して従前標準的治療方法とされていたCAP療法が効果が薄いことは既に指摘されていた。
△病院のN医師は、人の卵巣明細胞癌の細胞株に対する23種類の薬剤感受性を調べる試験を実施し、その結果、アクチノマイシンDが最も有効で、シスプラチンがこれに次ぐという結果を平成4年7月に専門誌に公表していた。
△病院は、同年8月20日第1回目の抗癌剤治療を開始し、同月24日終了した(以下、この第1回目の抗癌剤投与期間を「第1クール」といい、第2回目の投与期間を「第2クール」という。)。続いて△病院は、同年9月16日第2回目の抗癌剤治療を開始し、シスプラチンは第1クールと同量を5日間、アクチノマイシンDは一日当たりの投与量を半減して10日間それぞれ投与し、同月25日終了した。
Aは、同年9月28日個室に移され、寒さを感じるとして電気毛布を掛けていたが、当日のAの血小板数の値は、1万1000であり、第2クール開始前の値の約10分の1にまで下がっていた。
△病院は、Aに対し同日夜400CCの生血輸血を行った。
Aは、同年10月1日△病院において満72歳で死亡した。Aの死因は出血性ショックであり、その原因は、化学療法に用いられたアクチノマイシンDの副作用である血小板減少症であった。
そこで、◇ら(Aの遺族である夫及び子)は、Aが死亡したのは、医師らに診療契約に基づく債務不履行又は不法行為があったとして損害賠償請求をした。
原審(東京地裁平成9年4月25日判決)は、◇らの請求を認めなかった。そこで、これを不服として、◇らは、控訴した。
(損害賠償請求)
- 請求額:
- 遺族合計5005万円
(内訳:逸失利益1111万5622円+患者の慰謝料2500万円+遺族固有の慰謝料4名合計950万円+弁護士費用455万円の内金請求と思われる)
(裁判所の認容額)
- 原審の認容額:
- 0円(請求棄却)
- 控訴審裁判所の認容額:
- 遺族合計150万円
(内訳:遺族固有の慰謝料4名合計150万円)
(控訴審裁判所の判断)
医師の説明義務違反があるか否か
この点について、裁判所は、N医師のAに対するアクチノマイシンDの投与を含む本件化学療法は、研究手段又は実験として行われたものといえないから、N医師らにそのことに関する説明義務があったということはできないが、この化学療法は平成4年当時においては明細胞癌に対する標準的治療方法として確立したものではなかったと指摘しました。
この化学療法には、深刻な副作用を伴う蓋然性があることは良く知られていたと認められるから、仮にN医師らが、この化学療法の有効性を提唱した研究者であり、N医師らにおいては、この治療方法を採用したことに治療上の過失がないとしても、深刻な副作用を伴う生活ないし生存状況と癌の予後に伴う生活ないし生存状況や危険性等を衡量して、患者のクオリティー・オブ・ライフあるいはより楽な死への過程を考えた医療を選択するために、この種の先端的治療方法を採ることについて、患者等の自己決定を尊重すべき義務があり、そのためにAないしその家族に対して採用しようとする先端的治療方法について厳密に説明した上で承諾をとる義務があるというべきであるとしました。
そして、最初にAと◇1らに、化学療法の内容と必要性等を説明したのは、8月1日のS医師の告知であり、その際には食欲の減退、髪の毛が抜けること、口の中が荒れること、白血球や血小板の低下が生じることなどの副作用が発現することの説明が行われたが、S医師は、この化学療法は「5年ないし10年先を考えると、実施していた方が安全であり、また、必要な治療である。」として、本件化学療法の有効性と必要性を強調し、当時その治療方法が先端的なものであり、一般的な標準的治療方法として承認されていないという事実を説明していなかった。そのため、Aないしその家族の副作用の危険に対する認識が明確にならず、本件化学療法回避の選択をする余地をも考慮に容れた判断が困難になったものと推認されると判示し、S医師の化学療法開始前の説明は、必ずしも標準的治療方法となっていなかった治療方法を採用する場合の患者らの自己決定権を尊重すべき説明となっていたとは認められないと判示しました。
また、第一クールが開始した後の説明においては、◇1らに対するものであり、副作用の深刻さの説明もあったものと認められるが、既に第一クールが開始されている状況の下での説明であるから、同じくAらが途中で第一クールの本件化学療法の中止を申し出ることは事実上困難であると推認されると指摘しました。さらに、第二クールが開始される前までには、K医師ら主治医は、日常的な会話の中で、Aに対してある程度の説明を行ったと推認されるが、このような説明も、既に第一クールが終了し、医師らから血小板数等の著しい減少があったこと等の詳細な説明がない限り、アクチノマイシンDの投与による深刻な副作用や出血性ショック死等の危険性を考慮に入れた患者等の自己決定権を尊重する内容のものでなかったと認められ、説明義務を尽くしたとはいえないと判断しました。
以上から、控訴裁判所は、上記「控訴裁判所の認容額」の範囲で◇らの請求を認めました。