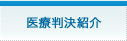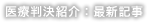東京高等裁判所令和4年7月6日判決 判例時報2553号12頁
(争点)
- 医師に説明義務違反があったか否か
- 医師に検査義務違反があったか否か
*以下、原告を◇、被告を△1及び△2と表記する。
(事案)
A(昭和19年生まれの男性)は、D病院において、遠位胆管がんと診断され、平成26年5月14日、幽門輪温存膵頭十二指腸切除の手術を受け、術後に、放射線照射の治療を受けた。Aは、その後、平成28年5月31日、転移が出現し、D病院において、化学療法を受けたが奏効しなかった。Aは、平成29年5月8日当時、D病院において、積極的な治療は行わず、症状を和らげる療法であるベストサポーティブケア(BSC)を受けていた。
株式会社である△2は、手術で摘出された患者のがん組織と△2が作製した免疫刺激剤を混合して作製されるワクチンを患者本人に投与する治療法を研究開発している(以下、上記の△2が研究開発したワクチンを「本件自家がんワクチン」といい、その投与による治療を「本件自家がんワクチン療法」という。)。
Aは、本件自家がんワクチン療法に関心を抱き、医療法人である△1が開設している△病院に対して本件自家がんワクチン療法について自ら問い合わせた。本件病院の担当事務員は、Aに対して、「がんの手術を受けた方、これから手術を受ける方のために 自家がんワクチンのご案内」、「自家がんワクチンQ&A よくある質問と回答集」、「がん治療の専門医も驚いた、効果のあった症例のご紹介 自家がんワクチン(AFTVac)」との表題の各小冊子を送付した。
本件自家がんワクチン療法の実施に際しては、本件自家がんワクチンを作製するために、△2に対して、患者自身の一定量以上のがん組織を提供する必要があるところ、Aは、平成29年4月24日、D病院に対し、本件自家がんワクチン療法を受けるために、同病院に手術により摘出されたがん組織が必要であるから、これをA又は△病院に提供するよう求めることを記載した書面を提出した、これに対し、D病院の医師は、同年5月8日、△病院のB医師(△1の被用者)に対し、Aが遠位胆管がんであり、平成26年以降、切除、放射線照射、化学療法等の治療を行ったが、今後はBSCの方針になっていること、Aが本件自家がんワクチン療法を受けることを希望して組織提供を求めているが、上記がん組織の提供は行わないこと、Aにもその旨説明して納得してもらったことを「報告書」と題するA4判1枚の書面により回答した。
Aは、同月15日、再度、D病院に対し、書面により上記がん組織の提供を求めたところ、同月19日頃、D病院から上記癌組織の提供を受けた。
Aは、平成29年5月19日、△1との間で診療契約を締結し、同月26日、△1に対し、治療代として145万4760円を支払った。
B医師は、Aが本件自家がんワクチン療法の予約を申し込んだ平成29年5月19日、Aに対し、A4判4枚の「△病院・自家がんワクチン療法・説明書」と題する書面(以下、「本件説明書面」という。)を交付した。
本件説明書面には、自家がんワクチン療法は臨床研究段階のものであり、必ず有効である保証がない旨の記載があり、B医師もその記載に沿って同旨を説明し、自由診療であることを説明した。他方、本件説明書面には、B型肝炎ウィルスに感染したことのある肝がん患者で、自家がんワクチンを投与した患者の方が投与しなかった患者よりも延命効果があることが統計学的に証明されている旨、副作用は軽いものはあるものの1900例以上の事例の中で問題となる重篤な有害事象は1例もない旨の各記載があった。
B医師は、Aに対し自分の経験上、本件自家がんワクチン療法には標準治療が終わった患者の中でも効果があったがんの症例があり、数年生き延びた人がいる旨を説明した。
B医師は、遠位胆管がんについて、本件自家がんワクチン療法が有効であったという症例がこれまで存在しなかったこと、B医師自身がこれまで本件自家がんワクチン療法が胆管がんに対して有効であった症例に接したことがなかったことのいずれについてもAに対して説明しなかった。
B医師は、何らの客観的な検査を行うことも、他の病院等における検査を指示することもなく、検査時点が約11ヵ月前と考えられる他病院からの情報提供及びAのKPS(患者の健康の度合いを0から100%で測定する指標であるカルノフスキーパフォーマンスステータスの略称)の状態や顔色等の外見のみから、Aに自家がんワクチン療法の適応があると判断し、本件自家がんワクチン療法を行う旨を告げた。
Aは、△病院において、B医師の診察を受け、平成29年5月29日、同年6月6日及び同月13日の3回、本件自家がんワクチンの接種を受けて、本件自家がんワクチン療法の治療を受けた。
Aは、平成29年8月11日、胆管がん、肝転移により死亡した。
◇は、Aの妻であり、遺産分割協議により、Aの△らに対する損害賠償請求権を単独で相続した。
◇は、B医師及び△2が共謀して、Aに対し、本件治療において必要な説明をせず、また、必要な検査を実施せず、Aを死亡させたと主張して、△らを被告として損害賠償請求訴訟を提起した。原審(宇都宮地裁令和3年11月25日判決)は、B医師の説明義務違反を認めて△1に対して損害賠償を命じた。
これに対して◇が控訴し、△1が付帯控訴した。
なお、◇は、控訴審において請求を死亡慰謝料から自己決定権侵害による慰謝料に変更し、請求額を減縮した。
(損害賠償請求)
- 原審での患者遺族の請求額:
- 852万4760円
(内訳:不必要な治療費145万4760円+不必要な治療を 受けたことによる慰謝料30万円+死亡慰謝料500万円+妻固有の慰謝料100万円+弁護士費用77万円)
(裁判所の認容額)
- 原審の認容額:
- 110万円
(内訳:慰謝料100万円+弁護士費用10万円)
- 控訴審での患者遺族の請求額:
- 302万9760円
(内訳:不必要な治療費145万4760円+不必要な治療を受けたことによる慰謝料30万円+自己決定権侵害による慰謝料100万円+弁護士費用27万5000円)
- 控訴審裁判所の認容額:
- 270万4760円
(内訳:治療費145万4760円+適応のない本件治療を受けたことによる慰謝料30万円+自己決定権の侵害による慰謝料70万円+弁護士費用25万円)
(控訴審裁判所の判断)
1 医師に説明義務違反があったか否か
この点につき、控訴審裁判所は、医師は、患者の疾患の治療のために特定の療法を実施するに当たっては、特別の事情のない限り、患者に対し、当該疾患の診断(病名及び病状)、実施予定の療法の内容、これに付随する危険性、当該両方を受けた場合と受けない場合の利害得失、予後等について説明する義務があり、特に、当該療法の安全性や有効性が未確立であり、自由診療として実施される場合には、患者が、当該療法を受けるか否かにつき熟慮の上判断し得るように、当該療法に付随する危険性、これを受けた場合と受けない場合の利害得失、予後等について正確にわかりやすく説明する義務を負うというべきであると判示しました。
そして、B医師の説明内容を全体としてみると、本件自家がんワクチン療法が有効である保証がないことについて一応の説明をしているものの、他方において、遠位胆管がんとは種類の異なるがんについて本件自家がんワクチン療法効果を上げている旨の記載のある書面を示し、自分の担当した標準治療を終えた患者の中にも、本件自家がんワクチン療法によって数年生き延びた人がいると説明するなど、事前に△病院がAに対して送付した小冊子の内容も相まって、遠位胆管がんに罹患し標準療法を得ていたAにも、本件自家がんワクチン療法が有効であることを示す実績があるかのような印象を与える説明もしているものといえると指摘しました。裁判所は、これに加えて、B医師は、遠位胆管がんについて本件自家がんワクチン療法が有効だったという症例がこれまで存在しなかったこと、B医師自身がこれまで本件自家がんワクチン療法が胆管がんに対して有効であった症例に接した事はなかったことのいずれについてもAに対して説明したことはなかったこと、現在のAの状態については何ら客観的な検査を行わず、外見と問診及び約11ヵ月前の他病院からの情報提供程度で判断しており、Aの現状の状況を正確に説明することができるとは考え難いこと、本件自家がんワクチン療法を受けることと受けないこと(すなわち、本件自家がんワクチン療法を受ける代わりに現状の緩和療法を受け続けること)との利害得失を説明したともうかがわれないことを併せ考えると、B医師の前記説明は、Aに対して、Aの病状がいかなるものであるかを正確に説明することなく、本件自家がんワクチン療法について、この説明の時点においてはほぼ唯一の選択肢であるかのような誤った印象を与えたものと評価せざるを得ないと判示しました。
控訴審裁判所は、したがって、B医師は、Aの病状及び本件自家がんワクチン療法について正確に伝えなかったという説明義務違反が認められるというべきであると判断しました。
2 医師に検査義務違反があったか否か
この点について、控訴審裁判所は、B医師は、Aが標準治療を終えたいわゆる末期がんの患者であること、最末期のがんについては、本件自家がんワクチン療法も対抗しきれないことがあることを知りながら、Aに対し、何らの客観的な検査を行うことも、他の病院等における検査を指示することもなく、検査時点が約11ヵ月前と考えられる他病院からの情報提供(しかもA4判1枚の簡略なもの)及びAのKPSの状態や顔色等の外見のみから本件自家がんワクチン療法の適応であると判断し、事前の免疫反応テストを行うこともせず、本件自家がんワクチン療法を行ったものであると指摘しました。
控訴審裁判所は、最末期がん患者の場合、がん細胞の増殖に、CTL(細胞障害性T細胞)の増殖が追いつかなくなるため、自家がんワクチン療法では対抗しきれない場合が生ずることは、本件自家がんワクチン療法に関与する△2作成に係る小冊子にも記載があることも併せ考えると、B医師には、Aに対して本件自家がんワクチン療法を行う前に、血液検査や画像検査などを自ら行い又は他の医療機関への受診を指示するなどしてその結果を把握し、Aに本件自家がんワクチン療法の適応があるか否かを判断すべき注意義務があったのに、これを怠った過失(検査義務違反)があるといわざるを得ないと判断しました。
以上から、控訴審裁判所は、上記「控訴審裁判所の認容額」の範囲で◇の請求を認め、その後判決は確定しました。